豚肉の歴史・・フードタブーの発生。
道庁のイベント手伝いで知り合いになった、日高で5000頭の豚を飼育する経営者とメールするうちに、豚について自分が何も知らないことに気づいて、図書館へ行き、牛や豚や鳥の飼育のコーナーに行く。「豚肉の歴史」(原書房 食の図書館)という本があった。ベーコンの原料さえ正確に知らない自分であった。豚のにわか勉強を始めた。
歴史上、豚肉は約7000年前、近東そして中国でユーラシアイノシシを家畜化したのが始まりと書かれてある。豚肉はその全部を食べられる。しかも「すべての食肉がそれぞれひとつの風味しかもたないのに対し、豚は50近くの風味を持っている」とローマ時代の博物学者大プリニウス(西暦29~79年)が書いている。しかも鳴き声以外は、捨てる部分がなく、血液でさえブラックプディングとして食す。
乳飲み子のローストが贅沢な豚肉料理らしい。北海道名物料理ジンギスカンも子羊(ラム)が成人の羊(マトン)より美味いように子供が美味しいんだ。残酷だけど。ギリシャ人は、ソーセージとして豚肉を多く食べていて、ローマ人は中国人同様、豚肉を健康に良くて、消化しやすい肉として「あらゆる食品のなかで最も栄養価が高い」(ローマの哲学者ガレノス)と断言。
ガレノスはさらに豚と人間の肉は味と匂いがとても似ていて「豚だと思いこんで食べたら人肉だった」という危ない発言もある。そういえば、中国でも魯迅の「阿Q正伝」に人肉入りの肉まんの話があったと記憶するが・・・。とにかくローマはあらゆる饗宴で豚肉が食された。子豚の丸焼きも出てきている。最古のレシピは「アキピウスの料理書」といい、奴隷の料理人を持つ裕福な貴族のために書かれて、その中にも豚肉料理が満載されている。*ポリネシアの食人種は人を「長い豚」と呼んでいる。
ローマ人はハムやソーセージはガリヤ(現在、フランス・ドイツ・ベルギー・オランダ・スイス)から輸入していた。ガリヤでは紀元前1000年前からハムを作っていたのだと。鬱蒼とした森林は豚を育てるには気候が良くて、豚を放牧しておいて、食べたい時に捕まえるのだと。燻製まで作っていた。
そういうギリシャ・ローマ・ガリヤ・中国で大人気の豚肉がなぜユダヤ教徒とイスラム教徒でフードタブーになったのかというのが次の話だ。
まずはユダヤ教徒。旧約聖書レビ記に、イノシシ(豚)はひづめが割れているが、牛やヤギのように反芻しないので、ユダヤ人にとって汚れたものだと。反芻する動物は植物から栄養を取り草食だけど、豚はありつければ何でも食べる。動物の死体も生ごみも排泄物も食べて町をうろつくので胸が悪くなると。別な学者は、古代ヘブライ人は豚は動物の分類に当てはまらない、割れたひづめを持つ動物(偶蹄)は草食動物なのに、そこから外れる。さらに遊牧民のヘブライ人は、勝手にうろつくのを好む豚より、群れで生きてくれる牛やヤギ・ヒツジを飼育するのに慣れていたと。なんだか私には屁理屈のような気もするが・・実際は、レビ記を書いた人間がただ自分が豚を嫌いだっただけで、それを一般化して作為したのではと思うがどうだろう?確かめようもない古い話だけど。物事は考える以上に単純なことが多い。学者の盲点だ。資料を出せないと認められない、下手したら主観だらけで学会追放の憂き目に遭う。「チベットのモーツアルト」を書いた中沢新一さんも教授会で東大就任を拒否られた。雑談でした。
紀元前2世紀、セレウコス朝シリアの皇帝は、ユダヤ教徒に豚肉を食べさせて、ユダヤ文化をヘレニズム化(ギリシャ化)しようとしたが、それを拒み処刑されたユダヤ人が多数いた。ヨーロッパは豚肉・ハム・ソーセージ文化であって、ユダヤ人は食品タブーの面でマイナスな局面に置かれていたのである。
次はイスラム教徒だ。ムハンマドは旧約聖書に見つけた食品タブーを踏襲したと、この本(豚肉の歴史)には書かれてある。ムハンマドはユダヤ教徒が自分たちの宗教に共鳴して新たに信者になってくれるよう、旧約の部分を真似た(ユダヤ教の食品タブーを)のではないかなと。しかし、これを食べたら毒だとか病気になる、死を招くと言う食べ物ならいざ知らず、なぜ、人類は食品に対してこんなにタブーを設けるのか?この本はアメリカ人の学者なのでアイデンティテイ-という単語が乱発されていて、少しうんざり。
しかし、動物と性格という観点から考えると、英国人作家ジョージ・オーエル(動物農場)では、豚のナポレオンはリーダーとして、動物を虐待する人間(農場主)を追い出すが、追い出した後は独裁者として君臨、ほかの動物たちに呆れられ、恐怖される存在になり、最後はほかの動物仲間を裏切って人間と結託、ワインがぶ飲み・連夜のどんちゃん騒ぎをしてジエンド。貪欲な動物として豚を描いている。


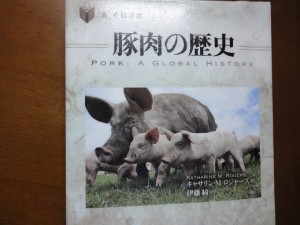
昔の少年。
ユダヤでもイスラムでもありませんが、我が第二の故郷北陸では何故か?豚肉を余り食べた記憶がありません。家庭環境にもよりますが、年に数回しか味わえなかったすき焼は当然乍ら牛肉でしたし、それも我が家では食べた記憶がありません。ぜいたく品で親戚の家で食べさせて貰って、その美味さに驚いたものです。豚肉は街に一軒の肉屋で売っていたかも知れませんが、それよりも鶏肉は自宅で飼っていた卵を産まなくなった鶏を父が絞めて食べさせてくれたのですが、子供ながら飼い鶏を残酷と思いました。その割に、野兎狩りはしました。冬は従弟の兄弟とスキーを履いて罠を仕掛け、早朝に掛かったウサギを獲りに行きました。従弟の兄貴分が雪はねのバンバ(硬い木製の板でしゃもじのお化けサイズ)でウサギの頭を一撃してぶら下げて持ち帰り、叔父さんが皮をはぎ肉を裁いてすき焼に。まるで鶏肉のように美味かったです。その他に他所の飼い犬を可愛がり、子供同士で山にウサギ狩りに連れて行きました。山で犬を離すと駆け上がり、匂いでウサギを見つけて吠えて巣穴から追い出して追いかけ最後はウサギの首をくわえて手柄を見せに来たところで犬の頭を叩いてウサギを奪い猟師の親爺さんに裁いて貰います。皮は猟師の親爺さんに、耳を二つ貰って役場に届けて、害獣駆除の礼金を当時で100円を貰い、肉は叔父さんに持って行くとすき焼で従弟たちと食べました。野鳥のツグミや寒すずめも罠を作って獲って焼き鳥にしました。鶏を残酷と思ったのにウサギや野鳥や魚は残酷と思わずに平気で食べていましたから不思議です。驚いたのは北海道に来て豚肉や羊肉を盛んに食べる事でした。個人的には羊肉が好きですね。羊肉の脂肪は体温で溶けやすく消化も良いのでツウジも良くなります。豚肉も良く食べるように成りました。牛肉は美味いのは分かって居ますが、正直なところ高価なので中々買えません。安い外国産は固いので食べる際は予めコーラに漬け込んでから焼きますね。でも消費比率から言えば、豚肉のバラ肉や切り落としが多いですね。
seto
こどものころは牛肉は見たこともありません。スキヤキは豚肉でしました。ビーフという単語に異常に私が反応するのも牛肉への憧れでしたね。コンビーフという缶詰があって、私は開けてそのまま食べました。馬肉が入っていましたね。ウサギの肉をずいぶん食べてますね。しかも狩猟からやってるのですごい体験をしていますね。ジンギスカンは安くて子供のころに食べましたが、近頃は高くて買えません。一番安いのはトンシャブで、自宅近くに放牧豚で料理するとんかつや「こなゆきとんとん」ができて、実に美味な店です。びっくりドンキーのアレフが経営しています。
アドマン。
トンしゃぶと言えば、或る知人宅では兄弟姉妹8名と両親で10名家族で豚しゃぶの油が浮いた汁もスープとしてみんなで飲んだと言ってました。確かに栄養価は有るのかも知れませんが、アクの出た残り汁は飲まない方が良いと忠告しました。どうりで家族全員が太って居ますが、そのせいではと?。
seto
豚シャブの油を飲む話、はじめて聞きました。うどんでも入れるならまだしもですね。確かに豚に近づく汁飲みです。クワブタクワブタ。
oldbadboy
ムスリムのハラルやユダヤのコーシャなどの食の戒律は、日本人より長い肉食文化から生まれたルールです。日本でもレバ刺しが禁止されたり、飲食店が食品衛生法で厳しく管理されてるのと同じように、屠殺から調理場の設備まで細かく決められていますが、できれば食べない方がいいとか、他に食べ物がない場合にはやむを得ないとか、運用は流動的です。最近では日本人でも、きちんと管理されていて健康的として、ハラル食材が注目されています。
日本のとんかつ屋に一人のムスリムが来て、ハラルメニューがないのを知ってとんかつを食べていったことがあったそうです。その後も何度か来るので、主人が「チキンカツを用意しましょうか」と聞いたら、「そうなったらこの店に来れなくなる。”やむを得ず”、”他に食べるものがない”状況になるために来てるのだから」と答えたそうです。
seto
ムスリムの食習慣って厳しいですね。ハラル食材やそのメニューについて広く運用されるようになりましたが、身近な店に、そういう店がないのでメニューを見たことがありません。食べてみたいものです。近所に美味しいとんかつやが開店。とんかつ屋の隣にまたとんかつやができています。ヒレカツとエビ、カキ揚げ大好き、これでは血糖値下がらず、不健康ですね。