空気を読んでも従わない(息苦しさからラクになる)(鴻上尚史)
「空気」を読んでも従わない(生き苦しさからラクになる)(鴻上尚史)
2019年4月に作家・演出家の鴻上尚史さんが岩波少年文庫に書き下ろした、青少年向け(大人が読んだらスムースに理解できる)に生き方を指南、アドバイスした。下記のような気持ちになったことがある読者を対象にしている。
・どうしてこんなに、人の頼みを断るのが苦しいのか?
・どうしてこんなに、周りの目が気になるのか?
・どうしてこんなに、先輩に従わないといけないのか?
・どうしてこんなに、周りに合わそうとしてしまうのか?
・どうしてこんなに、ラインやメールが気になるのか?
・どうしてこんなに、なんとなくの「空気」に流されるのか?
上の6つの気持ちを分析して、日本には「世間」と「社会」があって、「世間」は家族・地域・学校・クラブ・会社など平素、自分が知っている(または知られている)集団に属していることから生じる心の動き。たえず相手(世間)のゴリゴリ価値観に縛られて、自分の居場所を世間の中に置いて生きる。一方、著者は「社会」での生き方を提示。気持ち的に楽になるあり方を勧めている。「社会」はまったく知り合いのいない未知の世界。自分から進んで発言すれば意外な人に出会ったり、思いを同じくする人に遭遇する機会もあるかもしれない。そこが家族やクラスメートと一緒にいるようなリラックスできる場所。孤独や孤立を恐れない生き方だ。はじめは苦しい思いをするかもしれないが、一つだけの世間(仲間)だと息苦しさが増す。イジメや排斥の同調行為になりやすい。世間に従うにしても緩く所属する複数の世間を抱えているほうがいいとアドバイス。逃げる場所がある。昔のクラスメートとか趣味仲間とか塾での友人、よその学校の友人でもいい。とにかく一つの集団に金縛りにならないようスマホ時代だからこそ多いメールによるイジメ。メール1本で人が死んだり、殺すこともできる現実を見据えて欲しいと。仲間意識が強いということは、それだけ排他性も強いということ。そうして仲間はずれを作ることでより集団の力は強まる。ようやく見つけた私の敵というわけだ。声の大きいボスの指示で集団が動き出すかもしれない。この本は全国の小学校や中学に1冊は置いて欲しい本であると思った。大人についても・・・・・・
『強い世間に所属するあなたは強くなります。それはあなたが強いのでなく、あなたを支えてくれる《世間》が強いからです。私たち人間は弱いのでそういうもので自分を強くしますが、学歴だったり家系だったり一部上場企業だったりね。強いチームに所属すると、自分の実力は変わっていないのに、まるで自分が強くなったような気がするのと同じ。』。大人になっても上記のフレーズは生きている。別にあなたが作った会社でも媒体でも銀行や商社でもないのにね。ましてや自治体や国や・・である。ちょっとの間、おじゃましますと属しているだけだと思えば、心身健康は保てますね。


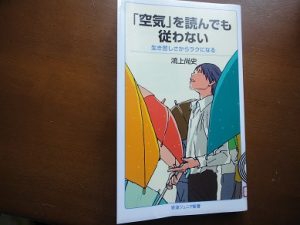
坊主の孫。
偉そうな人は居ますね。「何様?」虎の威を借る輩ですね。名刺の肩書にしても単なる活字に過ぎないのに、まるで勲章のように見せびらかしますね。或る農園の社長がくれた名刺の肩書には「百姓」と書かれていました。サラリーマンの名刺も部長とか課長とか次長とかは内々の位であって、社会では何の効力もありませんね。対外的には単なる「月給取り」とか「会社員」に過ぎませんからね。
seto
サラリーマンって不思議な単語で、サラリー(塩=昔、働いたら生命の根源塩をくれた?)が語源ですね。なので、拝金教の現代にぴったりの用語に変わったのでしょう。創業者社長ならともかくほぼ雇われ社長でしょう、雇われ部長と、雇われ課長、雇われ社員。名刺からプレジデント以外、不要にするともう少し楽な社会になるでしょうね。先日、中央官庁の人間と名刺交換居たら、たどり着くまで肩書が20文字ありました。○○庁○○部○○課○○研究所○○○◎ もう頭に組織の重圧につぶされる。それだけ官僚の人数が多くてその一人を特定するまでにい所属を細分化し続ける必要があるので、会場で名刺交換やってまして女性も参加『あなた出世しましたね』と言われて笑顔、盛んに名刺を配ってました。
seto
サラリーマンって不思議な単語で、サラリー(塩=昔、働いたら生命の根源塩をくれた?)が語源ですね。なので、拝金教の現代にぴったりの用語に変わったのでしょう。創業者社長ならともかくほぼ雇われ社長でしょう、雇われ部長と、雇われ課長、雇われ社員。名刺からプレジデント以外、不要にするともう少し楽な社会になるでしょうね。先日、中央官庁の人間と名刺交換居たら、たどり着くまで肩書が20文字ありました。○○庁○○部○○課○○研究所○○○◎ もう頭に組織の重圧につぶされる。それだけ官僚の人数が多くてその一人を特定するまでにい所属を細分化し続ける必要があるので、会場で名刺交換やってまして女性も参加『あなた出世しましたね』と言われて笑顔、盛んに名刺を配ってました。
流浪の民。
世間の付き合いは従うほどキリがありませんね。義理と人情も行き過ぎれば苦しくなります。若い時分に兄弟姉妹どころか親戚縁者も皆無の北海道に移住してホッとしたものでした。田舎の慣習も腐れ縁の友人や知人とも一切縁を切れた事で初めて孤独感も味わったと同時に自立心も芽生えました。誰にも縋れず、良くも悪くも、すべての行動や言動は自己責任ですからね。例え間違っていたとしても自分自身にとっては少しは強く成れたのでは無かったかと思いますね。
seto
私は札幌生まれの札幌育ちで10か月岡崎に住んだ以外札幌で、郊外都市にいまは住んでますが、義理人情の世界にいまも浸ってます。歩けば知り合いの誰かには遭いますし、電話も来るので渡世の義理ですね。しゃべっては自分の老いを遅らせています。
昔の少年。
子供たちもスマホ時代ですね。スマホと言っても本来の機能だった電話は使わなくなりました。SNSのLINEなどWiFi機能を利用した通信手段が主流ですね。ビデオ通話機能での複数の友人同士で同時に会話を楽しんだり、一緒にゲームに興じたりと、スマホはコロナ禍で臨時休校が続いた自宅待機期間には大活躍でした。良い事ずくめばかりでは無く、特定のグループ化には成りやすいですね。気に入った友人同士でしか群れないですから自然に排他的にもなりやすいですね。子供たちは今、スマホの中でグループ化しているようです。便利すぎる時代はもう逆戻りできませんから、時代に合わせた教育や指導が必要かも知れませんね。
seto
小学校3年の孫もスマホをしてますが、ラインでつながるのは5人と決めてました。私を含めて。親身性と排他性は裏表ですからね。『異的なもの』を感じると排除に向かうこと多いです。他人に大迷惑をかけるのならともかく、この程度で嫌わなくても・・・と思うことも。子供の社会は大人社会の鏡で、われわれの社会の在り方が問題だと思いますよ。鴻上さん、最近、同じテーマで対談本だしてますね。