家族はそれぞれ自宅の外に落ち着く場所が・・(?)
昨日に続きおひとりさま賛歌かもしれない。
向田邦子さんの短編のテーマの一つが、外にそれぞれリラックススペースと人がいて、みんな自宅にいるより伸び伸びしていて、ときに愛人がいたりして、事件らしきものが発生する。実はひとりひとりが孤独な毎日を送っている様子を描いている。夫や子供が家を出る月曜日、妻が晴れ晴れ、気持ち良くなるのもうなづける。本来、家族も他人同士が作る人工物だから人為的な存在・仕組みで、アチコチ壊れやすい。すべての犯罪は家族関係から生じるとまで言う人もいる。宇宙のブラックホールを探求するのもいいが、探求者自身の家族の足元は大丈夫か?それぞれが見えない家族や家庭を持っていたり、独り身だったり。その空間から社会へ飛び出してくる。
家族の中の危うさは古来、文学・戯曲でも普遍的に共有されてはいる。ハリウッド映画も、壮大な宇宙をテーマにしてその危機を乗り越える映画が実は父と娘の愛情がテーマだったり、ほとんど離婚率50%に迫るアメリカの日常の現実を背景に出てきているシナリオ、ホームドラマに急展開するストーリーも多い。
向田邦子さんは、最後は台湾での飛行機事故(カメラに凝りだしての撮影旅行であった)で51歳で亡くなった。私は昔から連続テレビドラマはほとんど見ないので、彼女の出世作「寺内貫太郎一家」は見ていないし、「北の国から」も見たこともない。NHKの「大河ドラマ」もほとんどみない。なぜだろうと考えると、そういう時間は(家族みんなで見る)という時間帯で、その過ごし方が少年時代から苦手であったのかもしれない。今と違いテレビは居間に一台しかないし。私の家にいまはパソコンを入れて3台のテレビがあるが殆ど見ない。
それこそ「ひとつ屋根の下で住むが、心はここにあらず」の人生を10代からずっと送ってきたのだと思うと納得がいく。向田邦子さんは40代前半で乳がんの手術を受けてから、再発に怯えながら丸山ワクチンも打っていた。ここに「向田邦子の恋」という本がある。久世光彦さんも「触れもせず」で彼女について本を書いていて、彼女は仕事が終わったら、ある時期から通い婚的な男性がいたと書かれてある。
その手紙も死後、妹の向田和子さんに公表されているが、「自分を写したカメラマン」と恋に落ちていた。彼には妻子がいるがいまは別居し、同居する彼のお母さんと彼のために食材を買い、料理を作り、仲よく夕食を食べていた。ここが彼女にとって落ち着く場所だった。彼女のドラマを批評も彼はしてくれた。脚が不自由になった彼は、自分がいるせいで彼女に余計な仕事を増やしたり、経済的な負担をかけていることに耐えられず後日、自殺したのではと推理されるが、原因は藪の中だ。
心浮き立つことのあとには淵がくる(向田邦子)
とはいえ、ある時期、彼女には自宅の外にそういう場所と時間があった。サラリーマンで会社の机に座っている方が自宅にいるより落ち着くと言う人をずいぶん知っている。理由をつけてなかなか自宅へ帰ろうとしない既婚者も多かった。赤ちょうちんへ行く酒好きも多い。世の奥様方も、きょうも市内のホテルでケーキバイキングに長蛇の列、がやがやお喋り楽しそうである。家庭に戻るよりずっとこのまま・・を願ってるかもしれません。ただいま恋愛中の人、結婚願望の超強い人には夢のない話で申し訳ない。
「虚の空間」が家庭で「実の空間」は外!?


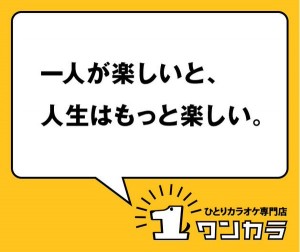
アドマン。
結婚は今では同性婚まで許容範囲の時代に成ってはいるのですが、古い我々は異性婚が常識の範囲でしたから、思春期を過ぎてやや暫くすると恋愛も幾つか経験し、苦い思い出も含め、身体と心のよりどころを求める結果として結婚を選ぶ事になります。つまり、生い立ちからの家族から離れて自分自身でまた新しい家族を作ろうとする訳です。それもその時点では理想的な家族をと。が、しかし結婚はお互いの自由を束縛する結果も大いにあり、暫くはお互いの我を通せても、やがてはどちらかに歩み寄らなければ共同生活が成り立たなくなったりギクシャクもしますから、余程に寛容な場合を除いて我の張り合いが延々と続くのでしょうが、それに耐えきれなくなれば今では半ば常識の離婚となります。そこまで割り切れる場合は、次の理想の?再婚となるのでしょうが、それすら面倒な場合は家庭に理想など求めず、反面教師で過ごしながら、本来の自分を外部に求める事になりますね。個人差はありますが、それが趣味の道だったり、仕事の延長だったり、異性だったりと。昔、外に妾を持つ男性は甲斐性が有るとまで言われた時代もあり、男性は堂々と遊んでいましたが、今や男性ならぬ女性も家庭の外に自由を求めている時代になって来ました。年齢に関係なく若い女性から中後年まで夢中になって追っかけしているのは10代・20代の若い男性タレントやミュージシャンのユニットです。そんな様子を何度か見に行きましたが、一般の若い女性に混じって家庭内の主婦や高齢女性までもが黄色い声援を張り上げ狂喜乱舞する様は女性の本性を見せられた瞬間でした。それに比べれば今の男性は正反対で大人しいようにも思えなくもないですね。これまでの古い考えの結婚も今では既に貴重な形になって来たのかも知れません。例えばこれまでとは全く正反対で女性が外に仕事や自由を求め、もはや男性が台所仕事や洗濯や育児など家事労働をする時代に入って来ているのかも知れませんよ。女房を尻に引くなどは死語で、男性は既に尻に引かれているやも知れませんね。
seto
基本はもともと、人間は一人になりたい生きものではないでしょうか? 社会なんてつくりたくなかったんだと思いますよ。せいぜい小さな家族で火を囲んでグータラグータラ食べて生きられればそれでいいという人生観があって、それを嫌々共同体や社会や企業を作って、欲望を駆り立てられて現代まで来て、さてこれからどうなるか、家族はどう変容していくのかというところに世界がきているわけですね。男社会の典型が六法全書ではないかと私は見ています。日本の社会が男社会、日本語や言葉遣いまで軍人を含めて作ったのは明治からの帝国憲法、戦後の法律各種、それを自在に操る官僚や弁護士や都道府県の役所職員、その根っこにある六法全書の有無を言わせぬ権力が社会を覆ってしまい、さらに個人情報保護法とか、自由度を締め上げる法律や条例が、ヤジさえ規制するんですからね。家庭でもヤジはケンカのもとになるし、しかし、ケンカあるだけ仲が良いともいえますからね。10代から六法全書みて、これ、日本語でないわとずっと思ってきました。社会常識が法律になれば、市民も弁護士も検察も警察も政治家もそれに従えばいいだけの話です。法律は減らしていくことが大事です。誰も言いませんが。殺してはいけない、人の者を盗んではいけない、人の妻を犯していけない、嘘をついてはいけない。この5つを守れれば健全に誰から見ても公明正大に生きられると思いますよ。それと自分の欲を制御することですね。男社会を作ってきた背景に六法全書があるんですよ。「俺が法律だ」という家庭や家族もありますから。日常生活を送ってる人にはろっぽ全書はありませんよ。確定申告のときだけ都合よく動き出すだけです。