飢餓から守る活動をする3人の日本人について。
昨日の続きである。核戦争があって、人類の大半が死滅することがあっても残りの人たちが再び農業を再開できるよう、現代版『食糧のノアの箱舟』がノルウエー最北のスヴァール諸島に築かれた。永久凍土の地下に200万種に及ぶ食糧の遺伝子情報を管理して、いつでも人類の食糧危機に対応できるよう、各国多くの政府と共有している(昨日のブログ写真参考)。
ベント・スコウマンはそこの所長である。ここで本書に紹介されていた3人の日本人がいた(現在もいる)。一人は岩手の盛岡で岩手県農事試験場に1930年から35年まで勤務していた稲塚権次郎(いなづかごんじろう)。『ダルマブーツ』と『ターキー』という2種の小麦を組み合わせて『農林10号』を日本の品種として育成した。何度も繰り返すメキシコ・アメリカの小麦危機を救おうと(緑の革命と呼ばれる)稲塚の育種した『農林10号』を米国農務省の代表がワシントン州立大学の研究室に届けられた。
小麦としては背丈が45センチと低いが、1946年占領下の日本から届けられた。これをアメリカの小麦品種と掛け合わせる仕事に着手。1950年代初頭になって、『農林10号・プレヴォー』が開発されて商用価値が出てきた。当時メキシコでは収量の多い病害に強い品種が好まれたが、いかんせん背丈が高くて強い風で倒伏した。短い背丈の頑丈な茎の小麦があれば解決できる。そうして選ばれたのが『農林10号・プレヴォー』で、これと背丈の高いメキシコの品種と掛け合わせて7年間の失敗を繰り返し、新品種を開発できた。成熟も早く、多くの種子もつけて、あらゆる気候に適応し、どのような土壌でもよく育ち、水の多寡も問わない。世界中のどんな緯度でも作れる品種だ。世界の飢えを救う小麦に成長した。日本人は彼のことをもっと知っておくべきだ。
『農林10号』をきっかけにして開発された小麦品種はこれまで飢えで苦しんだインドやバングラディッシュにも植えられ、食べられたのである。これもメキシコに本拠を置く『国際トウモロコシ・コムギ改良センター』の大成果であり、陰に日本人の稲塚さんの育種した『農林10号』が大貢献している。当時、この組織でタクトを振るったベントスコウマンの尊敬するノーマン・ボーローグ(最下段に彼の伝記がある)にはノーベル平和賞が授与された。飢えに苦しむ人々を助ける学者ボーローグに面接してベントスコウマンも働くようになったのである。
二人目は、田場佑俊(たばすけとし)という科学者である。同じ研究センターでスコウマンが小麦であれば、田場さんはトウモロコシを担当、スコウマンと密接に対話して品種改良や世界の飢えと戦ってきて、田場氏は現在もメキシコのセンターでトウモロコシ部門での研究で所長を務め、タクトを振るっている。
(写真を探したがグーグルに未掲載であった)
3人目は岩永勝(いわながまさる)。センターの財政や作物の遺伝子情報を独占しようとする民間の企業との闘いを含めて元CIMMYTの元所長であり、どちらもスコウマンから絶大な信頼を置かれた日本人である。もともと日本は農業立国であり(ちなみに戦前の農業従事者は50%、サラリーマンは30%)、稲や小麦の品種改良は昔から地味に研究を積み上げられている。
ただ、前回も書いたが、1品種だけの繁栄や多収穫では伝染病が襲うと一気に飢餓に見舞われる。食糧は未来に何が起きるかわからないから多様な品種を育てていなければいけないのである。私たちが口にする作物について、もう少し啓蒙的な番組や記事、未来の食糧を考えた、小さいころからの学校の授業を、投資の教えたりするより早い段階で教えないと、自然を離れて生きる子供たちが、毎日口にする食べ物がたくさんの人たちの品種改良によってなされているストーリーが失われる気がするのである。
昨日も書いたが『お金があれば食べれるわけではない。安全なタネがないと食糧はできない』ことを学び続けたい。『もし種が消えたら、食料も消える、そして君もね。』架空の未来談ではないのである。現在進行形の話である。しかも皮肉なことに小麦の原産地はシリアのアレッポあたりらしい。アフガニスタンあたりも。原油が出なければ穏やかな乾燥地帯に強い麦を栽培する中東になっていたかもしれないと妄想するときが筆者にはある。







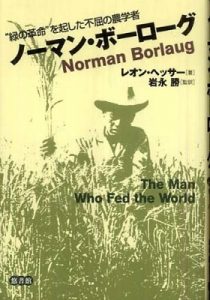
農業への理解。
食料問題に関しては「世界は一つ」なんですね。互いに争っている場合ではないですね。世界に貢献する人々が日本人にも居る事を知って感激です。子供たちばかりでなく,今の大人たちも,もっと農業を知らなければいけないでしょうね。
農業支援専門機と専門部隊。
アメリカや韓国その他の国に徴兵制度がありますが,その間,農業に従事する事を義務付けるのはどうですか?泥んこになって身をもって体験すれば,少しは理解するでしょう。破壊訓練と復興支援の自衛隊にも農業支援専門部隊も加えれば隊員も増えるかもしれませんね。銃の代わりに鍬や鎌を持って,戦車の代わりに耕運機やトラクターを習得して,除隊後も技能を生かせる教育ならどうですか。「国を守る」から「世界の食を守る」。これなら飢餓地帯への海外派遣も意義がありますね。農業機械以外は丸腰での派遣です。日本も意味もなくお金で支援するだけでなく,もっと真の世界貢献をして行かなければならないでしょうね。首相ばかりが海外旅行?でいい顔していないで。新千歳空港で,首相の海外旅行の準備のため旋回飛行をしている二機の政府専用機も,もっと納得のいく有効利用をして欲しいものです。機体に農業支援機と大きくメーキングをして。
seto
養老猛司さんが,霞ヶ関の官僚を半年でも1年でも田舎で働くことを義務づける提案を
しています。毛沢東が実は同じ発想で、都市のインテリを田舎へ下放させて、結果的に
2000万人を虐殺することにナッタリ、カンボジアのポルポトも大虐殺事件を起こして
しまいました。トランプ大統領にも、そんなにおいがします。エリート排除ですかね。
箸取らば,天土御世の御恵~。
宗教はどれも現世界の次の世界の予測を説いています。つまり,何時何時までにとは言えないでしょうが,このまま行けば現代の地球は必ず滅び行くことを予言しているわけです。その前に人類はフルイにかけられ,例えば「善・悪」で分けられ,死後の世界でも快適に過ごせるか,否か?と二分されると言われています。「死んでしまえばお終い」で皆平等で清算されると考える人が多いでしょう。アメリカ映画などでは,滅亡しかけた地球でたった二人の男女だけが生き残ったなどのシナリオもありますが,アダムとイヴの現代版ですね。これまで,地球上では局地的には全てが滅びて復興した事実は数多くあります。自然の力に淘汰される事は今後も予測はできますね。その時のためにも農業従事者や農業の研究者はもっと増やした方がいいと思いますね。僕たちの小学校には裏に学校田が,グランドの向いには学校畑。中学校では学校林もあって全校生徒で実習も楽しかったですよ。蛇のしっぽをつかんで振り回して友達を驚かせたり,山うさぎを捕まえて女先生に抱っこさせたり,遊び半分でしたが,作物も、植林も子供ながらに経験しました。楽しい学校生活でしたね。そして給食時間の初めには,みんな箸を合掌の指に挟んで,目をつぶって祈って感謝してからいただいたものです。農村地帯で食物も豊富でしたが,子供ながらに自然やお百姓さんや両親への感謝は忘れていませんでいたね。今では小学校で「道徳」の時間もあるようですが,その教科書の内容を見て,余りにも基本的?日常の常識程度でしたので,ガッカリしてしまいました。
seto
そもそも親たちから自然が失われていますから、ここをまずどうにかしないといけませんね。
自然はコントロールできない存在、一番の自然は天然ですが、生まれたての赤ん坊や子供も
そうですね。泣き出したらどうにも止まらない。管理や監視、言葉による支配には限界がある
ことを謙虚に認めることが大事だと思います。自然は人間に一切悪意は持っていませんし。
キリスト教もユダヤ教もイスラムももともと終末論ですからね。