人にはどれほどの土地がいるか(トルストイ・イワンのばか・・より)
トルストイの民話集「イワンのばか」(岩波文庫 中村白葉訳 75p~103p)(1885年)の3つ目の話に「人にはどれほどの土地がいるか」という話がある。
街に住む姉と田舎に住む妹の会話から始まる。姉は街での暮らしの自慢を始める。広々とした、きれいな家に住み、子供たちにも着飾らせて、美味しいものばかりを飲んだり、食べたり、芝居を見たり、遊び歩く自分たちの暮らしを自慢した。妹は悔しくて姉が嫁いだ商人の暮らしをけなす。自分の百姓としての暮らしを「変えようとは思わないわ。生活に派手さはないけれど、そのかわり心配というものがありません。あんたの生活は大きく儲けるかすっかりすってしまうかどちらかで、きょうは金持ちでも、明日は人の窓辺に立つこともあるわ。私の百姓仕事は確かなもんよ。暮らしは細いけれど長続き、ひもじい思いをすることがないわ」と。
姉も言い返す「ひもじい思いをすることがいなって?豚と子牛いっしょじゃないの。いい着物を着れるわけじゃなし、いいお付き合いができるじゃなし!お前のご亭主がどんなにあくせく働いたところで、けっきょくこやしの中で暮らして、その中で死んでいくんじゃないか。お前の子供たちだって、同じことになるんだよ」「それがどうしたとのさ。あんたがたの街じゃ、まるでみんな誘惑の中に暮らしているみたいなものじゃない。今日はよくても、明日はどんな悪魔に魅入られるかしれやしない。あんんたのとこの人だって、いつカルタに溺れるか、酒におぼれるかしれやしない。そうなりゃ何もかもおしまいじゃありませんか」
この会話を暖炉の上で聞いていた妹の亭主パホームが「わしらの仲間は小さいときから母なる地面を掘り返してきたんだから、ばかげた考えは起こしようがない。ただ弱るのは、地面の足りないことだ!これで地面さえ自由になったら、わしには誰だって怖いものはない。悪魔だって怖かないよ!」それを聞いていた悪魔は喜んだ。「よしきた、お前と勝負しよう。おれがお前に地面をどっさりやろう。地面でおまえをとりこにしてやろう」パホームは、女地主が自分の土地を売りに出す話を聞いて、自分の息子を作男に出したり、兄から借金をしてその土地を買った。作物はよく実り1年で借金を返し、本当の地主になった。
ところが、別な百姓の牛や馬が自分の農場に入り込んだり、迷惑を被ると、裁判を起こすが相手は無罪。村民や村長といさかいが続いた。「こうしてパホームは、土地は広く持ったけれども、世間を狭く暮らすようになった。」(82p)彼の周りに次々、商人や旅人が現れて、格安で広い土地の話をされて、パホームは買収に成功、農場も繁盛することになる。
しかし、最後はある村では、好きなだけの土地を格安で買える話を聞いて、さっそく金を用意して行ってみることにした。好きなだけとは言っても、日の出とともにスタート地点から歩いて、そして欲しいだけの土地を角に印をつけて曲がり、日没前に帰ってくるのが決まり。帰らないと全部没収される。スタート地点に村長の狐の皮の帽子が置かれた。パホームはぐんぐん歩く、歩く土地は全部自分の土地だ。しかし,喉は乾く、休憩してもいいが(1時間の辛抱が一生の得になるんだ)(99p)、その分、損をすると思い速足でも歩く。もう帰らないとスタート地点に戻れない。全力で戻り、「前のめりになりながらも帽子をつかんだ」(103p)倒れたパホームは口から血を流して死んでいた。村人は彼のために、頭から足まで入る3アルシンの穴を掘り、埋めた。「人にはどれほどの土地がいるか」より。
*必要な土地は自分の遺体が埋もれる大きさで十分なんだ。プーチンが読んで欲しいロシアの文豪の話だ。
似たテーマが「過ぎたる欲望は身を亡ぼす」で以前書いた。
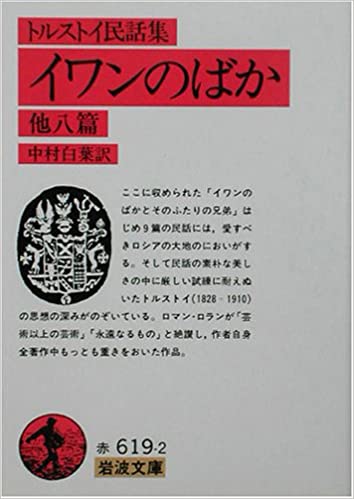


昔の少年。
幼い頃の農村の暮らしと青春時代の工場地帯や都会暮らし、そして今では自然にも近い環境の札幌郊外暮らし。一番長いここが暮らしやすい場所ですが、時々思うのは田舎への郷愁です。仕事から離れて移住してみたい気持ちも有る一方で、若い頃の怖さ知らずの冒険心が薄れて居ることにも気づきます。狭い庭を挟んでの街の暮らしに慣らされ過ぎて今度は広大な自然に囲まれての田舎暮らしに不安さえ覚える自分になっていますね。都会の若者たちの無謀とも見える移住ブームを羨むこの頃です。彼ら彼女たちも決して広い土地を欲しがっているわけでなく都会ならではの人間関係や孤独感から解放されたいのだと思います。
seto
美味しい空気、水、土地と畑、ノビノビ感を自分や子供に体験させてみたいサラリーマン多いですね。キャンプも疑似体験みたいなものでしょう。定年後の戸建て暮らしの人もあちこち30坪から100坪のの農地を耕して本州に住む子供たちへ作物を送ってますね。田舎は田舎でタイトな人間関係あるから、少し郊外のほうがゆるいかもしれません。知り合いに60ヘクタールの土地を持ち、ジャガイモつくってます。農家を辞めた人が隣の農家に畑を貸して。収穫のいくらかを現金でもらうらしいのです。隣町の千歳まで持ってます。若い働く労働者を欲しがってました。
坊主の孫。
過ぎたるは及ばざるが如し。ですね。欲は際限なく、土地も財産もお金も持てば持つ程増やしたい衝動に駆られるのでしょう。土地や財産やお金を増やす事は、その分を他人から頂いていることになるわけですから、幸福感に反比例して、その裏に泣く人々も大勢居るわけです。幸福は他人の不幸の上に成り立つものですね。
seto
幸福が他人の幸福と比例関係にあればいいのですがね。そうなりにくい。「足るを知る」という言葉が欲にブレーキをかけますね。「いずれ死ぬのだ」という教育を小さなころから教える大事さってありますね。広い土地も洪水になれば被害が何倍も増えるわけで、土地を持たなければ洪水には遭わない。次々と新製品を出す、過剰な消費社会になってますから、これを振りほどいて生きる暮すのは、子供にはむつかしいでsぃよう。まずはテレビを見ないで生きる工夫をしたいものです。