決断とリスクはワンセットであるほか(羽生善治)
2019年2月23日、BS1で羽生さんの特集を見ていた。そういえば昔、書いたブログがあったと思い出し、再録する。将棋の世界の怖さを知る。
この後は『日本の社会は、同質社会ということもあって、このバランスが悪いと思う。リスクを負わない人がいる一方で、リスクだけ背負わされている人がいる。決断を下さないほうが減点がないから決断を下せる人が生まれてこなくなるのではないか。目標があってこその決断である。自己責任という言葉を最近よく聞くが、リスクを背負って決断を下す人が育たないと、社会も企業も現状の打破にはつながらないであろう』(71p)(決断力 角川oneテーマ21)
格言の山のような本である。私は特に『リスクを負わない人がいる一方で、リスクだけ背負わされてる人がいる』というところで立ち止まった。日本社会を大局観として、将棋盤に見立てれば、起業家や企業経営者、派遣労働者も彼の視野に入って語ってるような気もしたのである。将棋はひとりで決断する連続技ある。
また『将棋と狂気』についても書いている。将棋を忘れる空白の時間、空白の大脳をつくる大切さについて説いている。仕事についてもいえることかもしれない。『将棋には怖いところがある。・・・将棋だけの世界に入っていると、そこは狂気の世界なのだ。ギリギリまで自分を追いつめて、どんどん高い世界に登りつめていけばいくほど、心がついて行かなくて、いわゆる狂気の世界に近づいてしまう。一度そういう世界に行ってしまったらもう戻ってくることはできないと思う。入り口はあるけれど出口はないのだ』(同著97p)
凡人には計り知れない怖い世界は、どの分野にもあって、仕事やゲームの世界、パソコンのソフト開発の世界もスポーツの世界にもきっとあるだろうなと推測する。サラリーマンでも仕事中毒や競馬に狂う、投資に狂う、夜の世界から出て来れない人にもある種狂気的なものがある。ドストエフスキーが『賭博への情熱』と命名した狂気の世界かもしれない。彼の場合はポーカーであったが。マージャンで賭けるものが無くなり、自分の妻を抵当にする小説もあったくらい賭博は世界中を駆け巡り、太古の昔から消えない遊び(真剣勝負)だ。
何事をするにも、何もしない時間や空間が大事。気晴らしを大切にとも読める本だ。狂気に陥らないために。
最後にチェスと将棋の起源であるが、起源は同じで紀元前2000年ころにインドで発明された『チャトランガ』が西洋に伝わりチェスになり、平安時代に日本に輸入されて将棋になったとある。中国や朝鮮、タイなどにも『チャトランガ』を基にする将棋があると薀蓄を語っていた。


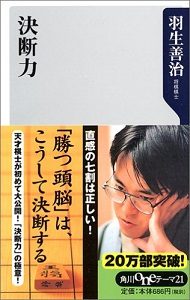
昔の少年。
将棋には無縁です。父親からも誰からも教わらなかったし、周りに将棋を指す人も居なかったですね。従って将棋の事は皆目分からないし、分かろうともしませんでした。最近では藤井君など新進気鋭の若者の棋士が世間の話題になっていますね。彼も幼少の時に祖父母から習ったようですね。古典的で厳しいプロ棋士の世界は現代の若者たちには?果たしてどのように映っているのでしょう。どんな世界でも若者のヒーローが誕生すれば、同じ年代の後継者も育って来るのでしょう。精神力と頭脳を駆使する将棋も囲碁も頭のスポーツとも言えますね。 そしてタイトル戦には企業が冠スポンサーとして参入し、棋戦数も増加していますね。一方、AIとの融合とも言うべき電王戦などでは、AIとの対決が話題になり、技術革新と共に現代にふさわしいゲームへの注目度も上昇傾向になっているようですね。
seto
私はコマの動き方くらいしかできませんが、NHKのテレビ中継は見ることがあります。若い人がヒーローで出てくれば、その世界は賑やかになりますね。政治の世界には聡明で賢い若者は皆無ですが、叫んだりあざけったり、ヘイトしたりする人間に群がる人たち多いですが、いずれ時間とともに消えていくと思います。ハーメルンの笛吹男や女には気をつけたい。新NISAで貯蓄より投資を煽っている岸田政権以来、投資をして老後を豊かにするという宣伝に煽られていますが、いずれ元金を失う羽目になるでしょう。亡くなった森本卓郎さん「早く投資の世界から離れなさい」。儲けるのは投資会社だけだと。しかも誰かを損させて自分だけ儲ける構造はすべてのギャンブルと同じだと。お金を稼ぐ方法は2つしかない、こつこつ働く労働か誰かから略奪すること。世界中がアメリカ流の投資社会になって投資バブルの最中で、いずれリーマンショックと同じ恐慌に入ると遺言してます。
アドマン。
将棋や囲碁など勝負の世界では緊張の連続でしょうね。その緊張感も狂気に近いほどの究極の集中力を必要とするのでしょうね。棋士などのように、勝敗の先の先のその先の深層に触れる視点を持つ人たちには「決断とリスク」は将棋や囲碁の戦略の永遠のテーマなのでしょうね。たとえば次の一手は「未来のリスクを見越しての究極の一手」だったり、また次の一手は「ひらめきの瞬間の決断の一手」だったりするのでしょう。どちらも絶えずリスクと向き合う知的かつ冒険的な一手なのでしょう。また、もっと掘り下げればその「リスクを美学として捉えたり、決断そのものを知的瞬間」とも考える哲学なのかも知れませんね。
seto
考えてみれば結婚も一人の異性を選び、ほかの異性を排除することですからね。大きなリスクまたはチャンスですね。選ぶことは捨てることです。