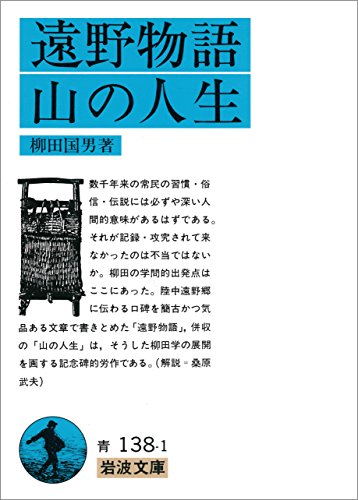『空想で見る世界より、隠れた現実の方が物深い』(柳田国男)
少し怖い話
『遠野物語・山の人生』(柳田国男著 岩波文庫)中、『山の人生』の最初に書かれている話を書く(同著93p~94p)。すでに読まれた人も多いと思うが、先日、古書店で見つけた小林秀雄『感想』(新潮社)にも引用されていた。『われわれが空想で見る世界よりも、隠れた現実の方が遥かに物深い』(柳田国男)。
今では記憶している者が、私の外には一人もあるまい。三十年あまり前、世間のひどく不景気であった年に、西美濃の山の中で炭を焼く五十ばかりの男が、子供を二人まで、鉞(まさかり)で伐り殺したことがあった。女房はとくに死んで、あとは十三になる男の子が一人であった。そこへどうした事情であったか、同じ歳くらいの小娘を貰ってきて、山の炭焼小屋で一緒に育てていた。その子たちの名前はもう私も忘れてしまった。何としても炭は売れず、何度里へ降りても、いつも一合の米も手に入れられなかった。最後の日にも空手で戻ってきて、飢えきっている小さな者の顔を見るのがつらさに、すっと小屋の奥へ入って昼寝をしてしまった。眼がさめて見ると、小屋の口いっぱいに夕日がさしていた。秋の末の事であったという。二人の子供がその日当たりのところにしゃがんで、頻りに何かしているので、傍らへ行って見たら一生懸命に仕事に使う大きな斧(おの)を研いでいた。阿爺(おとう)、これでわたしたちを殺してくれといったそうである。そうして入口の材木を枕にして、二人ながら仰向けに寝たそうである。それを見るとくらくらとして、前後の考えもなく二人の首を打ち落としてしまった。それで自分は死ぬことができなくて、やがて捕えられて牢に入れられた。この親爺がもう六十近くなってから、特赦を受けて世の中へ出てきたのである。そうしてそれからどうなったか、すぐにまたわからなくなってしまった。私は仔細あってただ一度、この一件書類を読んで見たことがあるが、今はすでにあの偉大な人間苦の記録も、どこかの長持ちの底で蝕(むし)ばみ朽ちつつあるであろう。
柳田国男は、明治35年から約10年、法制局に勤務して、囚人の特赦に関する仕事をしていた。そうしてこの事件の記録を読んで、『山の人生』の一番最初に入れたのである。『われわれが空想で見る世界よりも、隠れた現実の方が遥かに物深い』。私ははじめて『人間苦』という漢字に出会った。『山の人生』の前書きに、柳田国男は『天然現象の最も大切なる一部分、すなわち同胞国民の多数者の数千年間の行為と感想と経験とが、かつて観測し記録しまた攻究せられなかったのは不当だということ・・・』と述べている。大正15年10月の執筆なので、国内の学会は西欧の学問・学問へ猫も杓子もたなびく中、忘れられていく庶民の経験や言い伝えを残そうと奮闘するのである。新しい民俗学の始まりであった。常人という造語の誕生でもある。炭焼きの話に戻れば、自分たちがいるからかえってお父さんを苦しめているという子供の感情は、いまもあちこちの家族のどこかで流れているような気がするのである。それは、別にこの国に限らずあり続ける普遍的なことかもしれない。