道中の工夫は静中の工夫の億万倍。
商売の原点が行商にあるとしたら、歩きながら売る・工夫を繰り返すことだよという教え。近江・甲州・伊勢の商人に学べということなのだが、アイディアは歩いているときに沸き出ることが多いのは経験的によくわかる。よく動く人がまたいいアイディアを出す。様々な職業の人と飲み食いし、それも自腹でもいいから人付き合いしてた人も「なるほど」説得力のある企画を出していたね。
歩き、遊び、食べ、喋り、本を読み、孤独を楽しめれば怖い者は足元の奥さんぐらいだ。有名な京都大学に哲学の道があったり、ギリシャの哲学者、アリストテレスなどは「逍遥学派」とも言われ、歩くことの大脳へ与えるいい影響を古代から実証している。英国でも一番、高級な趣味が散歩であったのもよくわかる。少し、偽善的ではあるけれど。
歩きながら、次の植民地はアフリカのここでダイヤモンドを掘削しようとか中東のサウジで見つかった原油をロイヤルダッチシェルと相談しなくちゃとか考えて公園を散歩していたかもしれない。これでは悪巧みですね。こういうように、他人の大脳の中に入り込み、いま考えていることを映像で取り出せる機器が発明されれば、凄い世界になってしまうなと突然思う筆者。「静中の工夫」でも寝ながらヒラメキがあったりするんだけど、メモの習慣がないと起きたら忘れてしまう。
人間の歴史はヒラメキの積み重ねで前に進んできたようにも思う。火の発明にしても、雷がそれまでアフリカ大陸にたくさん落ちて、樹木を燃やしてそれをただ見ていたのが、ある人類の祖先が小枝を炎の中に入れて、火を移す発想(ヒラメキ)があって発明ということになった。獣たちも火には恐れを抱き、逃げる。肉食獣への武器も獲得したし、料理で焼いて食べるのを覚えたのだ。食べられていた人類が今度は食べる人類になって今に続く。(180万年前~50万年前での出来事、35万年前のネアンデルタール人は知っていた)
これも人類が歩いて、見て、ひらめいて、実行して、知恵となるパターンだ。行商の知恵の最古層が実は本来、人間にあるヒラメキ、少しひねって物を見てみる、別な観点で考える、ひねくれ者でいいから逆から考えると新鮮な視点にたどり着くかもしれない。
現実に戻れば、会議の中で発案された企画やアイディアは、どんなものであっても現場で試されていないから、商売ということになると試行錯誤だ。


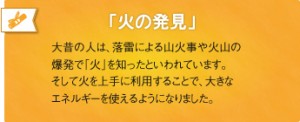
アドマン。
つまらない事と決めつけていた事が、実は一番大切な事だったと気付く事がありました。例えば、仕事の中では一番単価も低く、しかもいつ来るかも知れない名刺など印刷会社に直接発注すればいいのに?と面倒くさがっていたのですが、良く考えてみれば『何故?そんな仕事をワザワザ私を介して発注するのか?』と。最近、気づいたのですが、名刺は企業にとって大切なものだと。経営株主が変わり、代表者も変わり、間もなく人事異動が画策され、辞職させられる者、役職異動で上がる者、下がる者、配置転換者も多数出て、発注する企業内でさえも名刺が出来て辞令をご本人に言い渡すまでは最も重要な機密事項だと言う事です。つまり私自身が口外すればご本人はもとより社内や外部に機密情報漏洩となる訳です。発注者も人事部門のたった一人の人間だけが窓口で辞令通告日までは代表者と窓口担当者と私以外誰も知らない事になっている訳です。通常の名刺印刷なら発注者以外にもご本人様にもCCで確認校正の意味でメ―ル送信するのですが、このような場合は絶対やってはいけない訳です。言い換えれば、私に社内機密事項を誰よりも先に直接教えて来ていると言う事ですね。それには、私も暗黙の内に理解して決して口外しないし、それだけ信頼されていると言う事では無いか?と。この人事異動が全て完結するまでは、対象者ご本人の前では、何食わぬ顔でこれまで通りの対応をしなければならないと言う苦しさはありますが、じつは、つまらない仕事どころか私が信頼されていた事に今さらながら気づいたと言う訳です。企業内人事情報を誰より先取りできれば今後の仕事の動き方のヒントにもなり、私にとっても有りがたい仕事になったと訳です。やはり、どんな仕事にも手を抜かず全力投球ですね。
seto
名刺の仕事はありませんが、ある日まで秘密を通すのは大変ですね。口の軽い私はその任に堪えないです。社内人事でも公示日前にほぼ情報は出まくりでした。アドマンさん、さすがにプロですね。秘密はストレス溜めますから、できるだけ秘密は少なく、これからお互い生きましょう。
坊主の孫。
歩きながら、仕事をしながら、遊びながら考える事は意外に多いですね。ひらめきと言うわけです。ただジッと座って居れば何も危険ない目にも合わず、左程苦しむ事も無く、平穏に過ごせるのかも知れませんが、言い換えれば何も起こらないとも言えますね。つまり動くから、悩むから、苦しむから、学ぶから、遊ぶから、働くから、何かの問題が生じて何らかの解決策を考える事になる訳ですね。ぼんやりしていても、空や海や山や街を眺めているだけでも、又は会話の途中でも、何かのヒントが見つかる場合が有りますね。つまり動かなければ、何も起きないし、外部と触れ合わなければ変われないと言う事でしょうね。
seto
ひきこもりの子どもたちや大人たちは、外の刺激、運動から始まる変化を体感しないと、同じことをぐるぐる廻りで同語反復状態が続いて、外からの説教にキレルこと多いです。昨夜、川崎から帰ってきました。凄い人の混雑な都市でしたが、道路狭く、丘が多くて歩くのも難儀しました。フラットな大地が一番です。