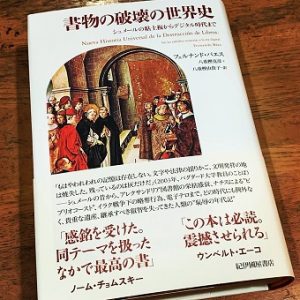書物の破壊(2回目) ペルガモン図書館と羊皮紙の発見!
『書物の破壊の世界史』の2回目は、ペルガモン図書館。エジプトのアレキサンドリヤ図書館は蔵書数約50万冊、大図書館(本館+別館)が炎上(紀元前48年)して破壊されたのは有名な話ではあるが、その原因には諸説あって、ローマによって焼かれた、キリスト教徒に焼かれた、イスラム教徒によって焼かれた、地震で崩壊した、国内の混乱で誰も省みなくなった、パピルス紙を使って筆者されていたから一度燃えると大炎上である。きょうはペルガモン図書館について。政治的にプトレマイオス朝エジプトと対抗して小アジア(現トルコ)にペルガモン王国があってエウメネス2世(BC197~BC159)はエジプトに対抗して図書館建設を長年にわたって実施、蔵書数20万~30万部に達した。しかし、当初、パピルス紙をエジプトから輸入していたが、敵対するエジプトはパピルスの輸出を禁じた。(現代のアメリカVS中国にも似ている)。そこで苦肉の策で発明されたのが羊皮紙であった。羊皮紙はしかも裏側にも文字が書けるから倍の文字数が収容できる。以降のヨーロッパで羊皮紙が使われた背景に、ペルガモン図書館の発明があったのである。しかし、冊数をアレキサンドリア図書館と競う余り、偽書も多くなってペルガモン生まれの医学者ガレノスは偽書をたくさん見つけている。さらに、図書館の司書たちも不都合な部分を削除していた。その図書館もローマの将軍アントニウスによって都が破壊され、蔵書がアレキサンドリアへ20万冊運ばれたという人と、破壊され瓦礫の山となったいう人もいる。きょうのブログは、手に入らなくなったパピルスの代用品として発明された羊皮紙が、後のヨーロッパの歴史を塗り替えた話でした。何が幸いするか、歴史をジャンプさせるかわからないということです。