帰る田舎がある強み。
敗戦後、大陸から軍人や民間暮らしの日本人が門司や敦賀に戻ってきた。まずは生まれ故郷を目指して汽車に乗り、北海道から九州まで運んでいった。父は南満州鉄道から帰国、北海道のニセコ(旧狩太)のジャガイモ農家に戻ってきた。兄嫁もいて、狭い空間ではあったが、食べるものもあり、寝る場所もあり、牛も1頭飼い、耕作する馬もいて、乳しぼりで極濃ミルクを毎日飲んでいた。敗戦後、都会では闇市ができて、とりあえず食料を確保するため、売れるものは何でも売って食料を確保した。一段落すると、今度は,仕事を求めて田舎から都会へ繰り出した。旧国鉄に就職した父は母とお見合い結婚をして、札幌に居を構えた。飲み水と洗濯は井戸を利用していた。札幌駅北口に並んでいた長屋街が新婚住居だ。台風でも来たら、潰れそな借家を見ると「ここからふたりの結婚生活が始まったんだ、そして産婆さんの手で僕が生まれた」と思うと胸がキュンとする。昭和26年の札幌の人口は324,0000人。私の人生のスタート地点だ。北14条西2丁目。地主の佐藤さんには子供がいなくて次男である私を養子に欲しいと言われたが父母は断った。養子になっていたら札幌駅北口あたりの大地主になっていたかもしれない。
長々と書いたが、「帰る田舎がある」がテーマだった。先日、落合陽一さんと養老猛司さんの「老いについて」の対談を聞いていて、養老さんが昔は学生が就職に失敗したら「田舎に帰ればいいさ」と思ってる人が多かったが、いまは帰る田舎がない人がほとんど。首都圏直下型地震や南海トラフの地震が起きたときに、一時帰宅でもできる田舎があるかどうか。そのとき食料や水、燃料、そして何より屋根の下で眠れる場所があるかどうか。移動できる足の確保ができるかどうか、田舎は田舎で彼らを受け入れてくれるキャパがあるかどうか。そんな心配をしていた。
お金持ちは早々と札幌にマンションを購入したり、他地域にもう一つの住居を持ち始めている。新型コロナが流行する前に、私は新千歳空港で地図を見ながら札幌のマンション探しに来たご夫婦と話したことがある。「札幌の町で地質的に安心な場所は札幌市電の内側。胆振東部地震のとき、ほとんど揺れなかった」と話した。東区は震度4であっても中央区はゼロに近い。マンション探しのご夫婦は数か所、ピックアップしていた。勉強熱心。旅をするときホテル代わりになるし。賢い選択をしている。子供や孫へ残せば彼らも利用できるし、災害時のセカンドハウスになる。
私の住む町に南幌町とか江別市があり、本州から古民家探して移住、コーヒ店やパン屋さんを開業する若者が増えている。日本ハムファイターズ本拠地の周りにマンションができていて、セカンドハウスとして購入する人(外国人)も多いと聞く。どちらにしろ、「田舎に住む」「第二の住処を持つ」ことができれば、生きてる間、安心して過ごせる可能性が上がる。娘と息子は借り家で生活しているから、いつ何が起きるかわからないのが人生。水が出て電気が来て、雨宿りでき、眠れる場所を生きている間守り続けようと思う。



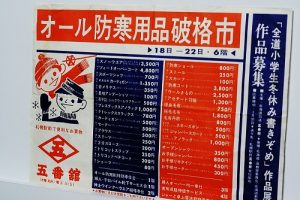
昔の少年。
東京から戦火を逃れて疎開した我が家の場合は父の田舎が有ったから良かったものの父の故郷が無かったらどうなっていたのでしょう。母方のルーツの千葉辺りに疎開したのかも知れません。それに父も東京と千葉の成田山で商売していましたから。我が家の有った東京にも近いし、東京の様な激しい空襲も無かったでしょうから、千葉が最有力でしょう。終戦直後の日本人はバイタリティーがありましたね。最悪の状況下でも何とか暮らして行くために最大努力をした訳です。例えば現在にあのような惨事が起きたと仮定すれば、果して今の人達にもあのバイタリティーは有るのでしょうか。せいぜい田舎に疎開すると言う考え以前に、きっとコンビニに買い出しに殺到するのでしょうね。多分、同じ思考回路の人達ばかりで、コンビニの棚の商品もあっと言う間に無くなるでしょうね。
seto
胆振東部地震のとき,人口7万人の恵庭市のコンビニは全道停電事情もあって、市内のすべてのコンビニは小麦粉まで即完売。電池もなくなり、ガソリンスタンドは自家発電を持つスタンドに超長い車の列ができました。物流が命のコンビニですからね。停電では高速道路の掲示板も真っ暗で、走れない。首都圏で災害(地震)起きれば、流通は麻痺して、食料の取り合いや餓死が100%発生しますね。金があれば食品を買えると思い込んでいる人たちですからね。埼玉の友人は札幌のどこかに住める中古の家を確保(それも逃げれればの話)したいと1月に真剣に言ってました。いかに異常な首都圏の人口やマスコミ本社集中かわかると思います。