自己充足は、あらゆる富のうちの最大のものである(エピクロスの箴言)
ギリシャの哲学者エピクロス(BC342~BC271)は、最高の精神的な快楽をアタラクシア(心の平静)に置いた。「平静な心境の人は、自分自身にたいしても他人にたいしても、煩い(わずらい)をもたない」死に関してもエピクロスの次のような言葉がある。「人間はすべてのことにたいしては、損なわれることのない安全を確保することが可能である。しかし、死に関してはわれわれ人間はすべて、防壁のない都市に住んでいる。人はだれも、たったいま生まれたばかりであるかのように、この世から去ってゆく」。「肉体の要求は,飢えないこと、渇かないこと、寒くないことである」富に関してもこう言う「貧乏は自然の目的(快)によって測れば、大きな富である。これに反し、限界のない富は、大きな貧乏である。十分にあってもわずかしかないと思う人にとっては、なにものも十分ではない」「獣にふさわしい仕事からは、たくさんの富がつみかさねられるが、みじめな生活が結果する」
そして自己充足の最大の果実は自由である。正義の最大の果実は、心境の平静である。
エピクロスのいう「自己充足」って具体的にどういうことなんだろうか?こういうたとえが出ていた。「知者は、困窮に身を落としたときでも、他人からわけてもらうよりも、むしろ自分のものを他人に分け与えるすべを心得ている。これほどにも彼の見出した自己充足の宝庫はすばらしい」。エピクロスは唯物論j者ではあるが質素な暮らしを旨とした。現代にエピクロスが蘇ったら、口をあんぐりしてどういう分析をいたすかですね。大都市の消費社会の乱雑さ・電気紙芝居から流れる音楽と映像に心臓麻痺を起こすかもしれません。都市で暮らして自己充足を達成するための手法は「引きこもり」でしょうね。亡くなった坂本龍一のピアノを「エナジー」から聞いてベッドに入るのもいいですが、70歳を過ぎると「自己充足は、あらゆる富のうち最大のものである」「自己充足の最大のものは自由である」「死に関してわれわれ人間はすべて、防壁のない都市に住んでいる」は至言です。
立花隆「死はこわくない」(文春)でエピクロスを引用していました。「あなたが死を恐れるときは死はまだ来ていない。死が本当に来たとき、あなたはそこにいない。だから死は怖れるに当たらない」(60p)


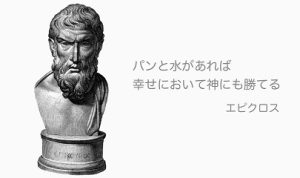
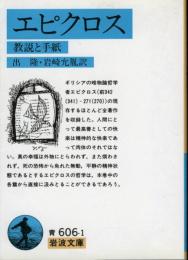
坊主の孫。
どんなに悪行を働いても、どんなに憎まれていたとしても、亡くなった途端に「あの人は良い人だった」とか「あの人はこんな良いところがあったね」とか善人に例えられるケースが多いですね。言い換えれば、死を持って終止符が打たれる事によって、この先は悪行も出来ないし、憎まれ口も叩かなくなる事がすなわち「良い人」に生まれ変わると言う事でしょうか。つまり死んでしまえばそれで終わりですから、当人はあがきようがありません。あの世とやらも有ると言われますが、未だ行った事も無いので死後は「無」としか言えませんが、せめて生きている短い間くらいは楽しんだり、喜んだりもしたいのが人間ですね。それと同等に悲しんだり苦しんだりも必ずありますね。また欲望も大きければ大きいほど、それらを無くした時の落胆も比例して大きくなりますから無理しない程度の身の丈に見合う生き方くらいが丁度良いのでしょうね。
seto
身の丈にあった暮らしがどこらにあるのか、ここですね。黒沢明が娘さんに「普通の暮らしが一番いいが、これが難しいいんだ」と言ってますが、まさにそうですね。老子や孔子が中庸、世界中の賢者がまったく同じことを言っているのは、自分の胸に手を当てれば、無理な背伸びの暮らしは後で大きなツケを払いますよという歴史からの知恵、人の身丈が民族を超えて存在する俚諺でしょうね。新聞はあってもテレビやネットのない時代に子供だった私でしたから、派手な有名にそっぽを向けます。地味や普通に生きる、地域の人と仲良く暮らす楽しさが一番です。