寛容のむつかしさについて
「窮鼠が成長したら猛虎になるかもしれない」(渡辺一夫)
フランス文学研究者の渡辺一夫さんが1951年に書いた「寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか」というエセイの中で、出てくる言葉だ。(筑摩書房 筑摩叢書 寛容について256p)。ローマ時代も新興のキリスト教徒が寛容なローマ帝国(数人の不寛容なトラヤヌス帝などいたが)に、ことさら殉教を大げさに説いて回り、凄惨の度を増してゆく。寛容って自分の感情をコントロールしなければならない難しい心的態度だと思う。
「キリスト教徒は後になって一大殉教神話を創作したけれども、事実は、この世紀全体を通じて(3世紀・筆者注)犠牲者は多くなかったのである。多くの残虐行為が(数人の)皇帝たちの行為にされているが、彼らの治下において、キリスト教徒が完全な平和を楽しんでいたことを我々は知っている」(J・Bビュリー 思想の自由の歴史 岩波新書)
311年と313年には宗教寛容令までローマ市民に発布している。ローマの寛容の代わりに気負い立ったキリスト教徒の不寛容が君臨するにいたったと古典学者のビュアリは言う。多神教であったローマが、キリスト教徒に短い期間に不寛容な政策を取ったがゆえに、相手に殉教者となる口実を与え、極めて危険で強力な武器を与えてしまったのである。ヨーロッパは中世、宗教改革を通じて、以降、殉教者のパレードで、いまでも殉教した聖人を崇める不思議な文化を持っている。
聖人になりたければ、殉教者になるのが手っ取り早いという文化。一神教では、原理主義のイスラム教徒にもみられる。戦中の日本も、特攻隊や幕末の白虎隊、江戸時代の忠臣蔵にしろ、「黙っていてもいずれ死が人間に訪れるのに、生きてて何ぼの価値観がなぜ、人類史を通して普遍化されていかないのか」。人間に本人に勝手な信念や自己理解や宗教的な吹き込みや思い込みや、本人が気付かない洗脳があったとしたら、またそれに基づいて日常の暮らしが行われているとしたらどうだろうか?他人から見たら狂っている、しかし、本人は周りが狂っていると思えばどういうことになるか。
他人から見たら狂信だけど本人は信念である。狂信と信念は紙一重である。そこはおさえておいた方がいい。狂信は相手に寛容になれないのが常だ。「普通人というのは、みずからがいつ何時に狂人になるかもしれないと反省できる人々のこととする。寛容と不寛容との問題も、こうした意味における普通人間の場に置いて、まず考えられねばならない」(同書251p)。太平洋戦争の間、ニュース映画を見るとシンガポール陥落や南京攻略のニュースで提灯行列をする国民の姿が見える。この場合、一緒に提灯を持って行進しない人は、変わり者・非国民というレッテルを貼られるので、嫌々ながらも参加した人が多い。
新聞社は簡単に右傾化した。むしろ煽り、部数を伸ばした。新聞用紙の供給で言論統制されたのである。(反政府的な記事を書くと用紙が配られず発行できないから自動的に政府の御用新聞になってしまう。いまの総務省から恫喝されるテレビ局の状況に似ている)。メディアは戦争が好きだ。自分を安全地帯に置いて書くからなおさらだ。スポーツ観戦記事と大同小異だ。自分が血を流さないからだ。
自由人(宗教改革やラブレー・エラスムス研究)の渡辺一夫は、東大のフランス文学研究室で苦悩していた(この辺は、加藤周一「羊の歌・上」東大仏文教室に詳しい)。狂信と信念も紙一重なら、正常と異常も紙一重だ、聖人と狂人も紙一重。窮鼠が猫を噛むだけなら可愛いが、猛虎になって殺戮を繰り返すのが現代だ。思い込んで断定的に憎しみ深く生きている人たち(個人や集団)を、他人を信用できて、柔らかく、穏やかな日常生活を送れるよう配慮する生き方を続けたいものだ。
あちこちで猛虎が跋扈しないよう祈るだけである。知らぬ間に私たちは数々の思い込みの中で(メディアや他人の言論の影響のもとに)生きていて、外の世界を知らない洞窟の中で生きているのかもしれない。一神教は一筋縄ではいかない難問題を(信者には問題とは映らない)2000年間、抱え続けているように思える。猛虎にさせないために、中世、15世紀に流行った格言。「潰走する敵の退路には黄金の橋・白銀の橋を作ってやれ」(同書 278p)そもそも潰走する敵を作らないのがベストなのは言うまでもない。ひたすら勇ましく、ひたすら高潔に、潔く憎み合う血みどろの宗教戦争の時代であった16世紀。逃げ道を作ってあげるのが、戦争を停止させる知恵だ。
現代日本は宗教戦争の時代だ。統一教会派閥、学会派閥、日本会議系統派閥、N国信者、ネトウヨ派閥、不倫文化を蹴散らす派閥。彼らの持っている武器は「教祖様の言葉や発言のリピート」SNSに長けたプチインテリ軍。


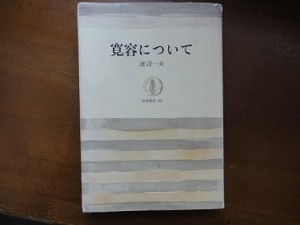


坊主の孫。
宗教戦争など宗教はとかく争いごとの根源のようにも言われていますね。50歩100歩と言えばそれまでですが、しかしすべてが同じでは無く、それぞれの良き部分と悪しき部分があり、後者だけを取り上げれば全て同じ結論に成りますね。前者の悪しき部分でビジネス化や洗脳などで戦争にまで導く、明らかに目に余るものは宗教を通り越して社会悪に成ってしまっていますね。平気で多くの人命を奪ったりなど問題外ですね。昨今の世界中のリーダーでさえ、同じような者たち揃いですから収拾がつかなくなっています。彼らに宗教的洗脳などが影響しているとしたならば、今後の世界中の宗教には法律が必要ですね。差別しない、殺戮はしない、はく奪しない、洗脳しないなどなど。人は人に対して寛容に成らなければならないと。普通の事なんですが?。世界中の宗教が特別扱いされて居るのも現実でその理由の根幹は、今や実在しない神仏の存在ですから、現世では実在する者同士で国際ルールを作るべきでしょうね。宗教の国債会議など今後も実現しないのでしょうか?せめて宗教の違いだけでいがみ合い殺し合うのだけはやめて欲しいですね。他人の命を奪う権利など誰にも与えられていませんからね。戦争すなわち犯罪ですから。早急なお互いの理解を望みますね。もう、うんざりです。
seto
「もううんざりです」が私の本音でもあります。一神教に限定するとユダヤ教のころから考えると3000年は続いています。秦の始皇帝ころもそうであればもっと古い時代からですね。火薬やダイナマイトの発明、飛行機やキャタピラの発明、銃の多様化、高性能化。もう発明品は全部、武器化する(それをつくる財力は国家が独占)。とにかく敵と味方論理(政治的思考)で相手を抹殺する原理ばかり。
昔の少年。
寛容についても戦争についても批判はいろいろ出て来ますが、解決策は中々出ませんね。解決に導く素晴らしい代案が無いからでしょうね。批判だけならいくらでも出て来るのが現状で、それも安全地帯での発言ですから、軍隊でも無いですが、最前線の肉弾戦の先頭に立たないで後方から囃し立てる軍曹のような意見ばかりですね。戦争や紛争を即座に鎮静化する事が出来るプロフェッショナルが欲しいものですね。
seto
撃たないと殺される場面で撃たないを選択できる人がどれほどいるかという判断でもあります。戦争ストッププロフェッショナルの育成を国連が果たせればいいですね。あらゆる宗教から選んでくる人材。書いていて虚しくなりますね、このテーマ。それでも書き続ける価値あるテーマですよ。
アドマン。
選挙戦でもSNSが勝敗を分ける時代です。例え間違った情報でも簡単に拡散出来てしまう。しかも従来の広告と違うところは安価に素早く。ネットにある情報は大半はフェークの場合が多く興味本位の偽情報で引き付けて最後に本題のビジネスに誘導するなど手口も巧妙に成って来ました。しかし、これほどまでに問題が多いと、今後はネットも果して効果的なのか?と考えてしまいますね。寛容と言えばネットは確かに誰彼かまわず受け入れてくれますが、返信がAIだとしたら正解とは限りませんね。AIの文書がところどころ変に成っている理由は日本語の難しさも有りますが、音だけで類似言語から選ぶため選び間違いが発生しますね。場合によっては大変な間違いを引き起こしますからネットには寛容すらありませんね。
seto
ユーチューブでは40分から1時間の長い討論番組を見ています。そのなかに、フェイクとか選挙における暴論やヘイトがなぜここまで他人の投票行動を動かすのか話合われています。断定的な物言いには気をつけたいのですが、自分で確かめる手立てがないので、つい大きな声を出す人の言説を信じてしまいます。そこには若い人を含めて不安感がそういう発言する人間に引き付けられる気がします。いつぞやオウム真理教や統一教会に入会した若者たちと同じ構造が見えてきます。カリスマ待望なのか、現代の社会をどんどん否定して、発言している人も多く、嫌老人(年金多額にもらい、楽な人生を送っているという誤解)の風潮があります。それを俺たち若者世代(正社員になれず、非正規で働く)がさらに支えていくのか?という批判ですね。