「獲物を取ったからといって威張るな」(アマゾンに住むマチゲンガ族)
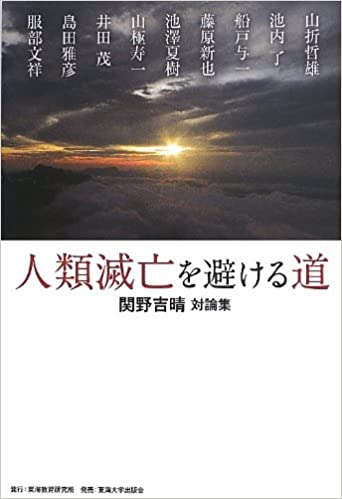
ペルーのアマゾンに住むマチゲンガ族と40年にわたって交流している医師関野吉晴さんの本に書かれてあった。平等を保つため、特に精神的な平等にも配慮したルールが昔からあって、「獲物を取ったからといって威張るな」が守られている。獲物は平等に分けられるのだが、精神の平等にも配慮されるのだ。威張って、ほら、俺が取った獲物だぞと渡すと、もらうほうが負い目を感じるのでそうならないように、獲物を取った男は尊敬はされているのであらためて威張らないよう家族や部族でルール化されている。「〇〇をしたから、威張る」という文脈は現代でも家庭内や様々な組織や社会や教育の場でも応用が利く話になる。「人類滅亡を避ける道」(東海大学出版133p)で作家の池澤夏樹さんに語った話だ。とんでもない格差社会が目の前にあって、二人の対談は「生きる上で、こんなにものは必要なのか」と限りない欲望の連打社会に警鐘を鳴らす対談になっている。アマゾンの未開社会から現代を照り返すと生きる上で別なルールが見えてくる。特に父性が強いユダヤ教やキリスト教やイスラム教の一神教世界に濃厚にこの現象が見えてくる。日本の家庭でも「俺が稼いだ金でお前たちを食わしている」とワンマン父さんが横行した時代があった。根っこは同じ「獲物(給与や肩書やメダル)を取ったからといって威張るな」である。


広告マン。
いいお話ですね。コミュニティのルールを守る彼らの精神を羨むと同時に尊敬しますね。こんな社会が広がれば随分住みやすい環境に成る事でしょう。オラがオラが村のような現代にはまるで別世界ですね。
seto
現代でもまだ地域コミュニティがなくなったとはいえ、私の住む団地では十分機能しています。何せ、独り暮らしの主婦が多いので身近に4人いますから、困ったことがあれば助けなければいけません。全員、同世代か年下です。一番怖いのは男の営業がやってくることだと彼女たちは言います。全員が顔を知っている社会ならそういうことはありませんね。せめて、行き来できる家庭を数軒は持ちたいものです。生きるところは勤め先ではありませんね。飲み会とゴルフ終われば簡単に解消される仲間でしかありません。