労働者の暇が搾取されている(?!)
19世紀、労働者の労働力が搾取されているというのは有名なマルクスの言葉。しかし、現代の資本主義は「労働者の暇を搾取する」ことで牽引されているといえるかもしれない。生きるだけで精一杯の父母の世代を思い返すと、小学校の運動会も父親は仕事で母親だけがバナナを持って参加していたのを思い出した。
それが今やイクメンと言われる、育児に参加したり、育児休暇を建前上、取れる企業も多い。それだけ「暇や休暇」を労働者の権利として取れる社会にはなったが、同時に休みなく働く癖が取れない人たちもたくさん知っている。私と同じ歳の社長へ「もう、そろそろ次の世代に企業経営を譲ってはどうなの?」とアドバイスしたら、「辞めてから、何をしたらいいの?することなんてないよ。」と反応された。しかし、これは笑えない現実で、世の中には「趣味」とか「好きなこと」が一見たくさんある人がいる。
仕事を趣味にすれば、稼げるし暇時間を潰せるし、他者との関係も保てるし、一石3丁である。しかし「暇や退屈」は普遍的に深い感情の中にあって、そこにつけ込むマスコミや媒体や広告代理店はイベントを次々発想して、出掛けさせ、金を使わせる。スポーツ行事や「いま、こんなことが流行ってると煽り言動をする」。極端な話、「自分の部屋でじっとしている」ことができないでいる。部屋にいてもネットで書き込みやメールをしていて、じっとしていない。私のブログもその類であるかもしれない。インターネットの普及やSNSも暇時間を持て余した人には最善の安い娯楽かもしれない。そして武器にもなる。
なぜなのか?「それは人類が退屈することを嫌うからである」。退屈もそうだけど「空白」を嫌う、空白な時間といってもいい。そこにつけ込むのが文化産業(アドルノ)。芸能やスポーツやゲーや読書、学問もそういう性格もあるかもしれない。講演の依頼に大学の教授室を訪ねたこともあるが、秘書の女性といちゃついて私を見て「おぬしは誰だ」と叱られたことがる。暇に任せて遊んでいたのであろうか。
暇な時間の使い方は意外に難しい。誰にも迷惑をかけないという前提で過ごすのは難儀をする。それで、与えられた楽しみ(テレビ鑑賞、準備され・用意されたイベント参加などに身を委ねる)で時間を費やして、安心を得る。なぜ、人は暇の時間に退屈をするのだろうか?退屈とは何か?私は退屈をブログを書くことで糊塗しているけれど(一日、50名前後の読者がいる)、毎日400字詰め原稿用紙を3枚程度にまとめる、テーマを決めるために社会の中をボウフラよろしく彷徨っている。過去の出来事の意味を再考したりして。もう少し誰かの役に立つ生き方を選択しないと罰が当たると亡き親たちから叱られそうだ。私も「自分の部屋でじっとしていられない」たちなのかもしれない。
労働者の暇が搾取されているというより、みずから外からの刺激に従順に応対しているだけだともいえる。そういえば、きょうも近所の花農家のガーデン祭りに行って、遊んできた。こうやって時間を使っているのである。テーマは変わるけれども、一人遊びの習慣を小さな頃から親が子供に教えれば,同調圧力が強過ぎる日本社会の中で、強く生きれる子供に育つと思うのだがどうだろうか?だから、暇や一人時間に何をしているかは、その人間の未来を照らすかもしれないぞと思いたい。


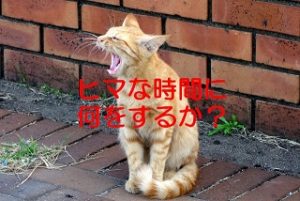
アドマン。
暇は恐怖ですね。何かしらやって居ないと不安に成りますからね。ですから今朝も3時台から目覚め、未だ動けば家族に煩がられるので再びベッドに。眠ってはいないけれど若干過ぎて時計を見ると4時に。もういいだろうと起き上がって家事を始めて炊飯、5時前にカーテンを開けて新聞をサラッと見て、寒くなったので朝はフリースを羽織って、薄い温かいコーヒーを入れて、風呂掃除してお湯を貼って、ワールドニュースなど観て、PC前に。時間つぶしが始まります。今日は晴れで少し時間も有るので頼まれていた他家の庭の草ぼうぼうの庭を芝刈り持参で10時頃から2時間程度作業予定を。兎に角、自営も仕事が激減して仕事が趣味の私には暇を持て余し気味ですね。しかし、考えて見れば高齢になって仕事量が少ないのは理に適っているとも言えますね。つまり、今まで仕事にかこつけて多忙で出来ないと断って来た事ができる訳ですから。雑用と思って居た家事や諸々の事にも気を配る様になりました。昨日は、花が咲かなくなった庭のアジサイの木を切って根を掘り起こしました。木は放置しておけば根が広範囲に伸びて排水管などを破損しかねないですからね。終活でも無いですが、庭じまいですかね。昨年の春先には桜の木も切りました。お蔭で、我が家では、これから秋の落葉も無くなりましたが、風で舞い込む他家の落ち葉掃きが仕事ですね。
seto
サラリーマン時代は、毎日毎日、することの連続でした。誰かと会えばアイディアを出し合って仕事をつくったものです。70才を過ぎて図書館ボランティアを2年半し,辞めたいま、大事なのは「あすすることがある』』あさって会う人がいるとか、仕事と外の人間とのつながりですね。本を読む冊数もどんどん増えてきています。心に刺さらない本は読まず返していきますからね。時間は大事ですから、無駄な本に時間を取られたくありません。芝刈り機を新しく買いました。前庭と後ろを借りましたが、草が器械が絡まって大変でした。伸びたと思ったら、人間の機械に切られるのですから彼らも大変ですね。それにしてもアドマンさんの労働範囲、広いですね。風呂掃除、ごはんづくり、隣の家の芝刈り、樹木の伐採までするのですか?ケガに気をつけてください。風の強い日は落ち葉が飛んできてガレージや自宅前道路に溜まっています。家に住むだけでも仕事は山のようにありますね。お腹が空いたら食事の準備と買い物です。一度、日本テレビ本社の制作室を見学したことがあります。全局のTV受像機を置いて、全国へ流すVTRを流しながらタバコをふかして足をだらしなく机の上に置いてプカプカしてました。この画面を全国の人が見ているのだと思うとTVそのものがバカらしく見えました。大宅壮一がTVは日本人を白痴化すると言いましたがむべなるかな。現代ではスマホは愚痴を悪口を大量発生させる機器かも。ブックオフでアカデミー映画10本で500円で売っていたので買ってきました。パールバック「大地」もありました。どんどん予定を、充実の時間を先に取り込んでおくと暇がダイヤモンドになります。
OLDBADBOY
江戸の町のしじみ売りは早朝魚河岸で仕入れて、朝食に合わせて得意先をふり歩き、朝のうちにその日の仕事は終わり。それで暮らしていけました。武士はもっとのんびりしていて、元禄時代の朝日文左衛門の日記によれば、月1回登城して殿様に挨拶し、弁当を食べて帰宅。翌月までは芝居を見たり、酒を飲んで暮らしていたそうです。仕事は畳奉行(それほど偉くなく、畳係程度のニュアンス)という役職だったので、数年に1度城の畳替えを差配するだけだったようです。今のIT企業は、日本のホワイトカラーの生産性が低いと言いますが、元禄時代より仕事効率が良くなるのか疑問ですね。
seto
落語の文七元結も魚売りではなかったですか?シジミ売りの江戸の下町風景ですね。朝で仕事おしまいがいいですね。豆腐も朝が早いです、學校へ行く途中、大豆のゆであがる匂いの中で登校しました。武士の仕事ぶりもすごいですね。大きな会社の役員や、非常勤取締役みたいですね。いまのIT企業の中を透明人間になって一度観察しに行きたく思いますね。クソどうでもいい仕事が大半かもしれません。ネクタイしてノートパソコン入れるバック持って、俺はいかにも仕事できる感を漂わせていますが、いてもいなくてもいいサラリーマンに見えました。彼に一度、(話し声がうるさい)と怒鳴られたことがあって、その復讐です。