子供の世界にあるアジールという場所

子供のころ、鬼ごっこでS陣取りをした。Sの字を大きく書いて、外に出るときは片足ケンケンで敵陣地へ向かう。外側に、チョ-クで〇を書いて、この中に片足を入れていると、敵方が来ても「安心」「安全」な場所となる。解放区みたいなところだ。権力が入ってこれない。捕まえられない。お互いがそのルールを暗黙のうちに知っていて尊重するのだ。
遊びの規則は、国の法律や会社の就業規則より曖昧さがない。遊びのルールは厳しいのだ。この「安全地帯」をアジールという。「避難所」「神聖な場所」とも。まだ、裁判制度が確立していない時代、身内が殺されたりしたら、被害者の親族には復讐権が生じて、どこまでも追いかけて加害者を罰することができる。しかし、加害者が「アジール」に入ると、追いかけた側はそこに入れない。45日間は外で待ってるしかない。45日間があれば、お互いが冷静になれるのでその日数を決めたらしい。それが、遊びにもなって、アジールは鬼ごっことして、世界じゅうの子供たちが遊んでいる。
ヨーロッパ中世史家の阿部謹也さんの「中世の星の下で」(ちくま文庫、315~322p)に詳しい。「ちょっと待って、ここは安全地帯だよ。勝手に入ってこないで」「この神聖な場所で、数字とか売上とか人事など俗世間の話はご法度」「ここは、一人静かにタバコを吸う場所。瞑想中につき話しかけないで」「夫婦といえども他人よ、あなたの都合で私を求めないで」(これはちと違うジャンルの話かな)。社会のあちこちに、こうしたアジールがあれば、昔の駆け込み寺のような機能が果たせるかもしれないし、イジメに遇ってる子供たちのアジールはひょとっとして、自分の親の説教から遠く離れた場所がいいときもある。
勤め人になったら、子供たちが自立して、親の近くであっても自炊して自分のアジールを形成するのは、凄いことなのだ。親の子離れを促進させる。いまはすっかり、近代国家は法律が整備されて、アジールは消失したが、上に書いたような疑似アジールは生きる上で大事なことだと筆者は思う。行きつけの床屋で、理髪師から「LINEで100人くらいとつながってるけど、先日、おまえなんでいいね!のボタンを押さないんだよ・・と叱りを受けたと。」。彼は「うるさいんだ!」と本音。
そうか、いまの時代、アジールの形成は勝手に外から電波で入り込まれて、難しい。電源を切るしかないね。しかし、緊急な用事があればそうもいかず、現代、アジールは、疑似でしかあり得ないのかと思うこのごろ。筆者にとってのアジールはどこかと考えたら、実は帰りの通勤電車の中だった。酔って何回も寝過ごしてしまったけど。寝ながら、夢の中で楽しい時間を過ごしていたのだ。


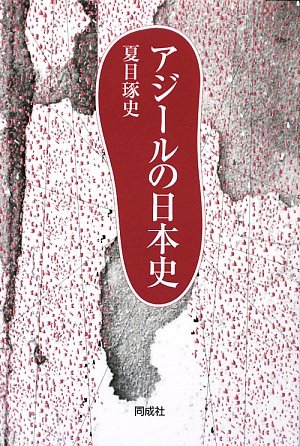

昔の少年。
子供の遊びにもその土地の方法があって面白いですね。私たちの場合は未だやや野蛮な遊びが沢山残っていました。子供同士は不思議なもので敵味方に分かれて戦ったかと思えば、次の日には普段通りに戻って一緒に遊んだりします。つまり戦いはゲームであってその時は敵でも本当は仲良しなのです。
seto
いい話ですね。戦いはゲームで敵味方、しかし本来は仲良し。多くの大人に聞かせたいですね。人間力から言うと、こどものほうが圧倒的に上ですね。頭脳が年齢とともに低下、特に情緒面で最近は最悪になりつつあります。メディア含めて。童話をもっと読んだらいいですね。
昔の少年。
遊びでも子供たちの中の年長のお兄さんが何かと皆んなの面倒を見てくれました。滋賀と岐阜と福井の県境の山頂に有る夜叉ヶ池に険しい冒険登山をした時も皆んなが彼の後について子供たちだけで成し遂げました。危険な登山でした。親たちは何一つ口出ししなかったです。今考えるに、あの登山口のある遠い村から更に山登りですから子供たちの足は丈夫だったんですね。当時はバスなど使わなかったです。
seto
冒険はいいですよ。年長は年少を守ってくれました。札幌市内では冒険といっても円山公園奥の幌見峠で昆虫採取くらいでした。豊平川でも遊びました、登山は円山で、最後だけきつい山でした。88か所の地蔵に石を置きながら登ったものです。