人にはどれほどの土地がいるか(トルストイ・イワンのばか・・より)
トルストイの民話集「イワンのばか」(岩波文庫 中村白葉訳 75p~103p)(1885年)の3つ目の話に「人にはどれほどの土地がいるか」という話がある。街に住む姉と田舎に住む妹の会話から始まる。姉は街での暮らしの自慢を始める。広々とした、きれいな家に住み、子供たちにも着飾らせて、美味しいものばかりを飲んだり、食べたり、芝居を見たり、遊び歩く自分たちの暮らしを自慢した。妹は悔しくて姉が嫁いだ商人の暮らしをけなす。自分の百姓としての暮らしを「変えようとは思わないわ。生活に派手さはないけれど、そのかわり心配というものがありません。あんたの生活は大きく儲けるかすっかりすってしまうかどちらかで、きょうは金持ちでも、明日は人の窓辺に立つこともあるわ。私の百姓仕事は確かなもんよ。暮らしは細いけれど長続き、ひもじい思いをすることがないわ」と。姉も言い返す「ひもじい思いをすることがいなって?豚と子牛いっしょじゃないの。いい着物を着れるわけじゃなし、いいお付き合いができるじゃなし!お前のご亭主がどんなにあくせく働いたところで、けっきょくこやしの中で暮らして、その中で死んでいくんじゃないか。お前の子供たちだって、同じことになるんだよ」「それがどうしたとのさ。あんたがたの街じゃ、まるでみんな誘惑の中に暮らしているみたいなものじゃない。今日はよくても、明日はどんな悪魔に魅入られるかしれやしない。あんんたのとこの人だって、いつカルタに溺れるか、酒におぼれるかしれやしない。そうなりゃ何もかもおしまいじゃありませんか」この会話を暖炉の上で聞いていた妹の亭主パホームが「わしらの仲間は小さいときから母なる地面を掘り返してきたんだから、ばかげた考えは起こしようがない。ただ弱るのは、地面の足りないことだ!これで地面さえ自由になったら、わしには誰だって怖いものはない。悪魔だって怖かないよ!」それを聞いていた悪魔は喜んだ。「よしきた、お前と勝負しよう。おれがお前に地面をどっさりやろう。地面でおまえをとりこにしてやろう」パホームは、女地主が自分の土地を売りに出す話を聞いて、自分の息子を作男に出したり、兄から借金をしてその土地を買った。作物はよく実り1年で借金を返し、本当の地主になった。ところが、別な百姓の牛や馬が自分の農場に入り込んだり、迷惑を被ると、裁判を起こすが相手は無罪。村民や村長といさかいが続いた。「こうしてパホームは、土地は広く持ったけれども、世間を狭く暮らすようになった。」(82p)彼の周りに次々、商人や旅人が現れて、格安で広い土地の話をされて、パホームは買収に成功、農場も繁盛することになる。しかし、最後はある村では、好きなだけの土地を格安で買える話を聞いて、さっそく金を用意して行ってみることにした。好きなだけとは言っても、日の出とともにスタート地点から歩いて、そして欲しいだけの土地を角に印をつけて曲がり、日没前に帰ってくるのが決まり。帰らないと全部没収される。スタート地点に村長の狐の皮の帽子が置かれた。パホームはぐんぐん歩く、歩く土地は全部自分の土地だ。しかし,喉は乾く、休憩してもいいが(1時間の辛抱が一生の得になるんだ)(99p)、その分、損をすると思い速足でも歩く。もう帰らないとスタート地点に戻れない。全力で戻り、「前のめりになりながらも帽子をつかんだ」(103p)倒れたパホームは口から血を流して死んでいた。村人は彼のために、頭から足まで入る3アルシンの穴を掘り、埋めた。「人にはどれほどの土地がいるか」より。
*1アルシンは0.711m。
似たテーマが「過ぎたる欲望は身を亡ぼす」で以前書いた。
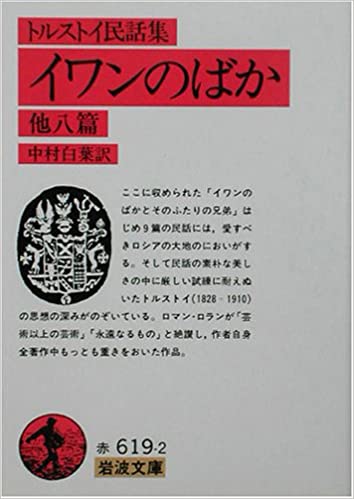


広告マン。
欲のないバカのイワンとその正反対の兄たちの物語は面白いですね。欲はキリが無く、もしもその欲を満たしたとしても最終的には欲が身を亡ぼす教訓ですね。土地も金も、決して欲しがらず、むしろ求められれば何のためらいもなく差し出すイワンには悪魔さえ尻尾を巻いて地中に隠れてしまいましたね。欲が無いと言う事は本人が十分満たされていると確信していると言う事で、決して贅沢する事で得られる満足感とは全く質が違いますね。バカのイワンの場合は王様になっても元通り田畑を耕し食べるに困らず、金銭など必要としない社会にする事で、金に物を言わせる事も出来ない状況を作ったのですね。働かざる者食うべからずとばかり、手にマメの無い者は食べてはいけない。手にマメが無い者は食べ残しを食べよと。
seto
イワンのバカに詳しいですね。自足している以上にお金も物も土地も要らない生き方ってすごいですね。そして手に豆をつくって働く。大脳にたくさん皺を作って、他人が作った食べ物を金を出して買い続ける行為(都会のサラリーマン)がいつまで続くやらです。土地を金や権力と読み替えても、通じる話かもしれません。イワンが一番、ぜいたくな人生を送っている、誰の指図も受けず、満足な生き方をしているようです。不平不満がないんですよ。これでは悪魔が出てくる隙もないです。都会人は手に豆がない人がほとんど。指先にキータッチで豆が出てくるかもしれません。
ゼロ戦パイロットの弟。
自分たち家族を養うだけの田畑さえあれば何とか食べて行けると言う事ですね。父の人生と重ねて考えていました。父は長男でしたが若い時に田舎から家出をして京都で丁稚奉公をして食いつなぎ、神戸で貨物船にのって北海道や遠くは中国まで行っていたそうです。その後、東京に降りて陶器職人の修行に久谷や桐生など転々とし絵付けなどを身に着け、北海道は小樽の米問屋の若旦那が立ち上げた陶器の会社に全国各地の職人の一人として呼ばれて手宮の洞窟の象形文字をあしらった「小樽焼」を。その後美瑛で十勝石を砕いて混ぜた生地で「十勝焼」を試みたりした後、東京に戻り、所帯を持った後に自分の窯を持って東京と成田で店を開いていたそうです。兄や姉たちは何不自由ない暮らしだったようですが、今のウクライナ同様、第二次世界大戦の開戦がすべての暮らしを変えてしまい、兄は師範学校を勝手に中退して予科練に志願し霞ケ浦から飛行兵に。父は軍需工場で潜水艦の冷却装置の製造に携わっていたそうです。戦火が激しくなり、仕事も住居も放り出したまま一家で父の故郷に疎開しました。米軍の東京爆撃でこれまで培った財産も家も仕事もすべて無くしてしまいました。私は疎開先の田舎しか知りませんが、姉たちは東京暮らしを忘れられないのか大きくなって皆んな揃って東京に戻りました。父母はそれこそイワンの馬鹿同様に僅かの田畑と山林を借りて半農半林の暮らしが始まりました。そんな父を或る者は「腑抜けになった」と陰口を叩きました。しかし今になって考えると疎開先での暮らしは正解だったと思います。確かに貧しく不自由でしたが、多くを望まなければ自給自足で食べて行けたわけですし、田舎でのコミュニケーションほど温かな物はありませんでしたね。母は故郷の東京に戻りたがっていて、しょっちゅう東京に行っていましたが、田舎育ちの私は、東京暮らしなど知らない事もあって、いつも父の傍にいました。幸い兄も生き残って無事復員し 、貧しいながらも一時的には家族全員での幸福感も味わいました。父はイワンのように王様にはなれませんでしたが、財産とは全く無縁の終戦後の我が家でした。悲惨な戦争を体験している兄姉たちでしたが、長男も長女も亡くなり、田舎暮らしの経験も遠い昔話になろうとしています。「人は皆、それぞれの山河に戻る」ですね。
seto
いまは、家族全員を食べさせるだけで大変な時代です。耕作地や農地があって米と野菜をつくれる広さと種があればいいのですが、そうであれば理想的なトルストイの描くイワンのような人生観を持てるでしょうが。お父さんの人生は読んでいるだけで、戦争に翻弄されて、自分のしたかった焼き物や陶芸の世界から離されていく辛さが伝わりますね。戦争もそうだし、津波や地震などの大自然災害で命を落としたり、家を流されたり、360度、人生を狂わされた人たちも多いです。故郷へ帰り、子供たちや家族を食べさせるために,農業と自給自足に近い暮らしを支えてきたわけですから,すごいことです。どこかで焼き物の世界で大成させたかったという気持ちはありますね。しかし、お父さんの背中を見てきたわけで、ゼロ戦パイロットの弟さんは何かを学んでいると思いますね。お父さんは生き続けているわけですよ。