日本の庶民の家屋はあけっぴろげであった。《第1回》
『逝きし世の面影』(渡辺京二)平凡社ライブラリーから
江戸の末期から明治の中ごろまで、いったい庶民の暮らしは初めて日本を訪れた外国人にどういう第一印象を残したのか。またそれは、書いた外国人自身の母国での暮らしや生活や価値観をも同時に表現するものであり、条約を結びに来た人、医者を含めてイギリス人、オランダ人、スウエーデン人、アメリカ人、イタリア人、オーストリア人、ロシア人、中国人(林語堂)などの残した文章を丹念に拾い集めて590ページにわたって江戸庶民、明治時代の庶民の暮らしを記録した名著である。『江戸時代の重要特質のひとつは人びとの生活の開放性にあった。外国人たちはまず日本の庶民の家屋がまったくあけっぴろげであるのに、度肝を抜かれた。』(同書155p)落語に出てくる長屋を想起する。『家は通りと中庭の方向に完全に開け放たれている。だから通りを歩けば視線はわけなく家の内側に入り込んでしまう。つまり家庭生活は好奇の目を向ける人に差し出されているわけだ。人びとは何も隠しはしない』(156p)(ヒュブナー オーストリア外交官の明治維新1887年刊より)『家屋があけっぴろげというのは、生活が近隣に対して隠さず開放されていることだ。従って近隣には強い親和と連帯が生じた。家屋が開放されているだけではなく、庶民の生活は通路の上や井戸・洗い場のまわりで営まれた。子どもが家の中にいるのは食事と寝るときで、道路が彼らの遊び場だった』(157p)家の中が見えるから、夫婦ケンカも見ることができる。
『開放されているのは家屋だけではなかった。人びとの心もまた開放されていたのである。客は見知らぬものであっても歓迎された。』(158p)『下層の人びとが日本ほど満足そうにしている国はほかにない』(イタリア海軍中佐アルミニヨン・イタリア使節の幕末見聞記1866年)『日本人の暮らしでは、貧困が悲惨な形であらわになることはあまりない。人びとは親切で、進んで人を助けるから、飢えに苦しむのは、どんな階層にも属さず、名も知れず、世間の同情に値しない人間だけである』(同書)開放的で親和的な社会はまた安全で平和な社会でもあった。だから戸締りをしない、する必要がない。明治23年来日したドイツ人宣教師ムンツィンガー『私はすべての持ち物を、ささやかなお金も含めて、鍵をかけずにおいたが、一度たりともなくなったことはなかった』(ドイツ人宣教師の見た明治社会)蔵には施錠はあったが。大森貝塚を発見したモースの名著『日本人の住まい』で、彼は錠、差し金、自動式掛け金を取り付けたアメリカの家屋は、日本人の目には監獄そのものに映るに違いない。
私が育った昭和30年代前半、札幌駅の北口で生まれた筆者でも、家は鍵をかけないで、他人の家を自由に行き来し、遊び場は道路や公園で夕食まで外にいた記憶がある。困った人があれば大家さんがお金を貸したり、縫い物の仕事を出してアルバイトをさせて暮らしを助けていた。ちゃぶ台用のミカン箱と布団2枚を持って始めた両親の結婚生活も、共同井戸で洗濯をしたり、水汲みをして生活していた。秋田県出身者北大生の寮もあって、私の遊び場であった。食べ物をくれる人たちだった。
著者の渡辺京二さんは、『日本の近代が前代の文明の滅亡の上に打ち立てられたのだという事実を鋭く自覚していたのはむしろ同時代の異邦人たちである。チェンバレンは1873年(明治6年)来日して1911年(明治44年)に去った人だが『日本事物史』を古き日本の墓碑銘と刻んだ。本の題名が『逝きし世の面影』とつけられたゆえんである。
14章に分かれていて、1、ある文明の幻影 2、陽気な人びと 3、簡素と豊かさ 4、親和と礼節 5、雑多と充溢 6、労働と身体 7、自由と身分 8、裸体と性 9、女の位相 10、子どもの楽園 11、風景とコスモス 12、生類とコスモス 13、信仰と祭 14、心の垣根
もうこの時代には戻れはしないが、せめて心くらい、開放的になるよう日々努力したいものである。陰惨な事件は激減すると思う。


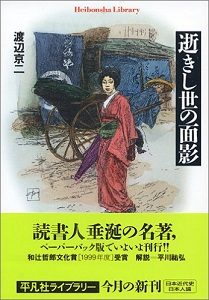
デロリアン
僕は北海道で最初に感じた事は、①言葉は標準語に近い。②女性の言葉は下町風で男性的。③一部の地域を除き,住宅に塀が無い。でした。本州ではそれほど裕福でも無い普通の家に塀がめぐらされていました。それに比べて北海道は開放的だと感じましたよ。
seto
私が住んだことのある国鉄の官舎は4年間、長屋でしたが、隣の部屋とベニヤ1枚。毎日、夫婦ケンカ
と物が飛んで壁にぶつかる音を聞いていました。すさまじい夫婦でしたが、会うと普通の挨拶をする。
いまならベニヤ1枚で区切る家は少ないでしょうね。大きな声なら会話も全部聞き取れましたね。塀の
ある家は、私は東区育ちですが、稀です。地主さんだけでしたね。
楽しき日々。
東京から戦火を逃れて父の田舎に疎開した我が家は、親戚の使っていなかった家を借りて住み始めました。元々長男坊の父は母屋を弟にあげてしまって、丸裸で、しかも5人の子供と一緒に故郷に戻ったことになります。そんなおじさんの家にも住めず、父の又いとこの空き家に年間3万円の家賃で暮らしました。いい人ばかりで、隣のタバコ屋のおばちゃんも反対隣の酒屋のおばあちゃんも、我が家の家族を度々お風呂に呼んでくれました。テレビもよその家で見せて貰いました。おやつもくれました。僕ができることは列車に乗ってお使いに行くことくらいですが、お駄賃をくれて、駅前で大好きな小豆アイスキャンデーを一本買って汽車に一人で乗れるので最高でした。大人たちは鉄道員か田畑や山林で働いていて日中は子供のことは放任主義でした。子供同士での遊びもいろいろでした。玩具らしきものは全くありませんでしたが、山や川や神社の境内や校庭で楽しく遊んだ幼少期でした。